在宅鍼灸って知ってる?
HAMT=Home-visit Acupuncture and Moxibustion Therapist
代表:白石哲也氏により打ち出された、在宅鍼灸療法士育成プロジェクト。
今後、需要が高まるであろう在宅鍼灸の領域において、プロフェッショナルとして活動をする鍼灸師を育成する目的で活動している。
現在はnoteで¥1000-/月額で、これまでの100記事を超える在宅鍼灸に関する記事がで読み放題の『HAMT〜在宅鍼灸師のためのライブラリ〜』を提供している。

【対象】
主に在宅鍼灸師1−3年目の若手鍼灸師が対象。
内容としては治療院やトレーナー、ベテラン鍼灸師など様々な人でも非常に学びを深めることができるようなコンテンツ。【具体的なサービス内容】
白石氏noteより引用(一部表現を改変)
在宅における各分野のプロフェッショナルによって投稿される記事を読むことが出来る。
具体的な分野は下記となります。
⚫︎フィジカルアセスメント
⚫︎リスク管理
⚫︎経絡治療
⚫︎中医学
⚫︎泌尿器
⚫︎etc..
約3日に1度のペースで更新されるこのマガジン、在宅鍼灸の現場で活躍する鍼灸師たちや、専門分野のプロフェッショナルから生きた学びを得ることができるのはとても魅力である。
そんな魅力的なHAMTではあるが、本当に生きた学びを得られるのだろうか?
ということで、はりらぼ学生部の現役の鍼灸学生ライターが飛び出してHAMTの魅力をレポートしてきました!
※この記事はHAMTとはりらぼ!のタイアップ記事です。
・さえ
鍼灸学科2年生
高校時代腰痛の治療を受けたことをきっかけに鍼灸を学びたいと思うように。今は鍼灸の機械的刺激・温熱刺激が症状の改善に影響を及ぼすことに面白さを感じている。
どの科目も好きだが、特に東洋医学の考え方をもっと知りたい。
犬派。
・りさこ
鍼灸学科2年生
レディース鍼灸やメンタルケアなど幅広く人に寄り添える鍼灸の魅力に惹かれて鍼灸師を目指すように。
旅行と猫が好き。
◯がんや慢性疾患の倦怠感をケアするために
 りさこ
りさこ倦怠感はかなり身近であり、自分自身も倦怠感の症状改善として治療を受けたことがあるため、臨床の場でたくさん関わるのではないかと思いこの記事を選びました。
 まりな
まりな確かに「何だか全身が疲れているんです」って言って来院する患者さんは多い気がするな〜
 りさこ
りさこはい。記事には倦怠感の説明からがん関連倦怠感の分類とその対応、そして倦怠感に対する鍼灸の可能性について書かれていました。
 まりな
まりな”倦怠感に対する鍼灸の可能性”!何だか記事の内容が気になってくるワードだね!
 りさこ
りさこですよね!記事に書かれていたのですが、倦怠感はよくみられがちな症状が故に医者側から優先順位を低くされてしまったり、患者さんが否定してしまい見過ごされてしまう場合があるそうです。
 まりな
まりな倦怠感って痛みを生じているわけじゃないし、目で見てわからない症状だから、なかなか理解してもらうのは難しいよね。
 りさこ
りさこ優先順位が低くなってしまうのは想像がつくのですが、患者さん側が否定してしまうというのは盲点だったなと思いました。また、「だるい」という言葉には地域に土着した表現があるので知っておく必要があるというのも、合わせて覚えておきたいと思いました。
 まりな
まりななるほど。患者さんとの会話から、本人も自覚していなかった倦怠感を読み取るのも鍼灸師さんの役割かもしれないね。
 りさこ
りさこまた、記事によるとがん関連倦怠感の治療は一次的であれ二次的であれ明確に効果があるという治療方法はなく、だからこそ鍼灸が臨床で活用できる可能性を秘めているそうです。研究が進めば今以上に鍼灸のがん患者に対するニーズが増えていくと考えられるので、注目していきたいです。
 まりな
まりな明確な治療方法がないからこそ、鍼灸治療が期待されているんだね。もし、がん患者さんに対してのニーズが増えたら、緩和ケアにも積極的に取り入れられるかもしれないね〜
 りさこ
りさこはい!こちらの記事は、二次倦怠感に対して鍼灸師として注目すべき項目や実際の臨床において大切にしたいことなどが具体的に書かれていて、とてもタメになる記事でした。ぜひ皆さんに読んでいただきたいです。
◯がん患者さんの食欲不振について~悪液質を知ろう~
 さえ
さえ今回私は、親族にがんを発症した者が多いことに加え、ついこの間、大学の先生からがんの緩和ケアのお話を聞いたばかりというのもあり、いなとらさんのこちらの記事を選ばせていただきました。
 まりな
まりな緩和ケアは在宅鍼灸をやっている鍼灸師さんとも関わりが深そうな分野だね。記事ではどのようなことについてふれていたの?
 さえ
さえ今回の記事では、がんの患者さんによくみられる症状である「食欲不振」、そしてその中でも「悪液質に伴う食欲不振」についての基礎を学ぶことができます。
 まりな
まりな「悪液質に伴う食欲不振」かあ…。さえちゃんは「悪液質」って言葉は聞いたことがあったかな?
 さえ
さえ私は授業で「悪液質」という言葉を聞いたことがありましたが、恥ずかしながら「痩せてしまう」という程度の認識で知識不足だったので、今回こちらの記事で、悪液質とは何か、飢餓とは何が違うのかを知ることができてとてもよかったです。
 まりな
まりな「悪液質」って普段生活していても耳にする機会が少ない言葉だよね。記事で確かめることができたのは、いいことだね!
 さえ
さえはい!私は、こちらの記事を読んで、鍼灸ががんを根本から断ち切り治すというようなことはできませんが、患者さんが普段感じている、食欲不振などの不調を和らげたり、継続的なコミュニケーションを取ったりなど、QOLの向上に貢献できるということを学びました。
 まりな
まりなうんうん。
 さえ
さえまた、その働きかけをするには、患者さんに関わる他の医療業種との連携を密に取ったり、自分が鍼灸師として患者さんに何ができるのかという情報を集めたりすることが必要だということも記事にありました。
 まりな
まりな鍼灸で治せないものもあれば、鍼灸だからできることがあるよね。鍼灸師だからこそできることを探しながら患者さんに関われるといいよね。
 さえ
さえ自分や、親族など近しい人ががんを患って、情報を求めている人はたくさんいますが、同時に誤った情報も多いと思います。医療に携わる者として、鍼灸師は正しい情報を正しく理解することにより注意を払わなければならないと思いました。
 まりな
まりな医療従事者の一人でもある鍼灸師自身が、がんに関しての情報を正しく理解していることが大事だね。
 さえ
さえはい!がん患者さんや慢性疾患の方をみていく上で、悪液質や食欲不振について基礎から見直したいという方に是非読んでいただきたい内容です。
 まりな
まりな緩和ケアに関する知識をぜひ知識で学びにいこう〜!
HAMTに興味をもったら
高齢化社会が進む今、訪問鍼灸領域はますます需要が伸びていくことが想定される。
鍼灸師として幅広いフィールドで活躍するためにも、今のうちに知識と視点が広がるこれまでの100記事を超える在宅鍼灸に関する記事がで読み放題の『HAMT〜在宅鍼灸師のためのライブラリ〜』に登録してみてはいかがだろうか。

| お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 白石哲也 | @physio_tetsuya |

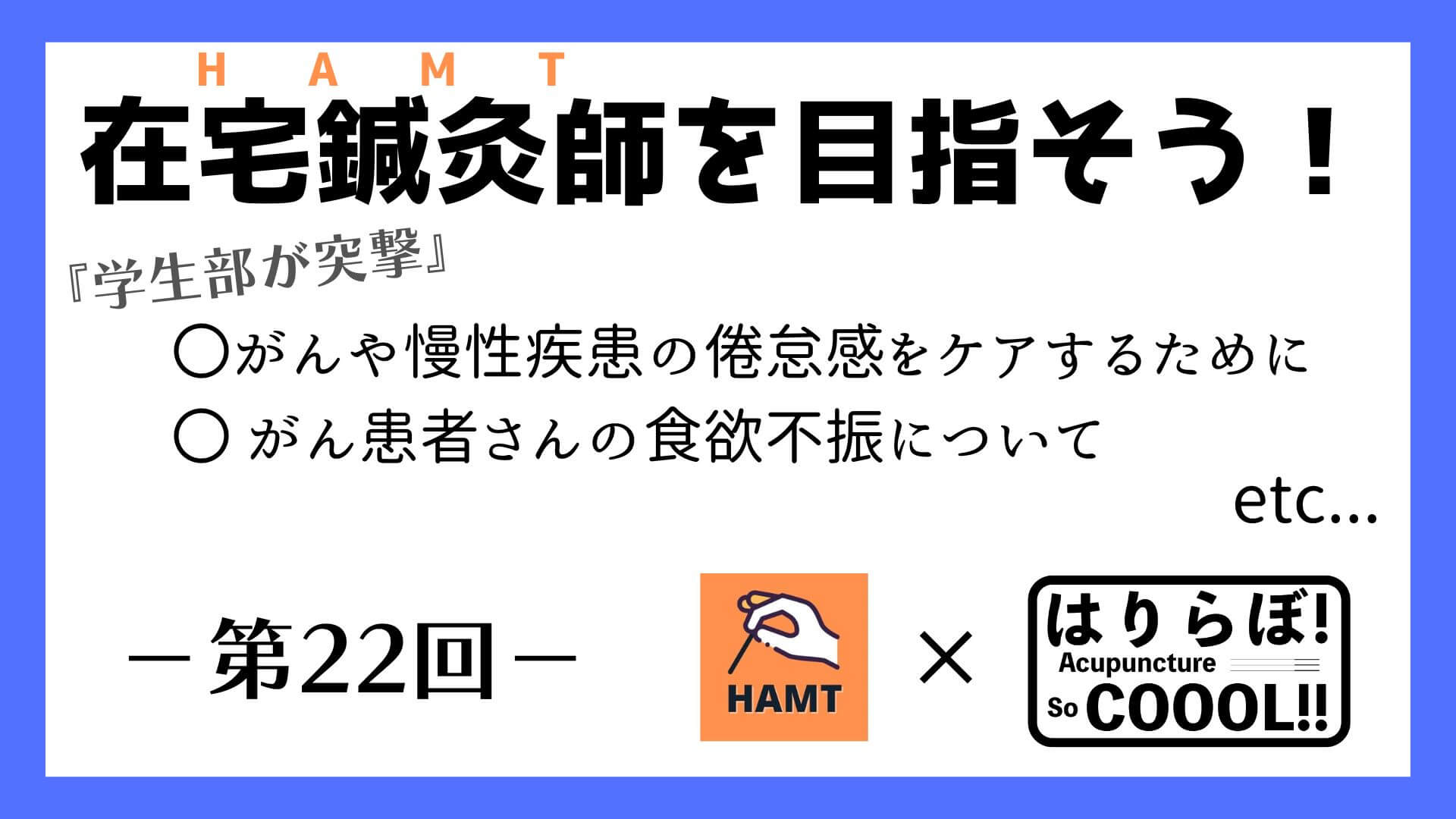


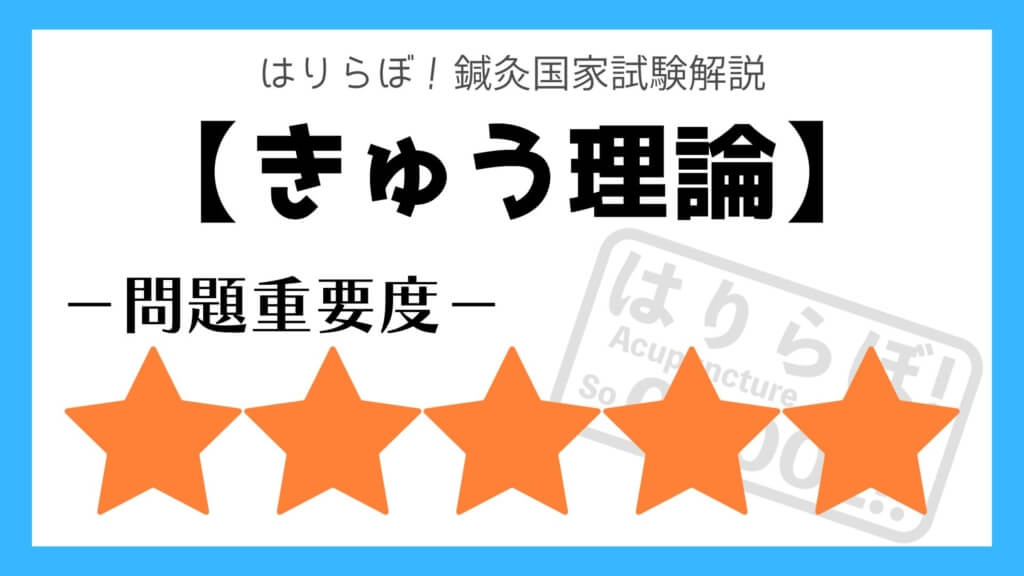
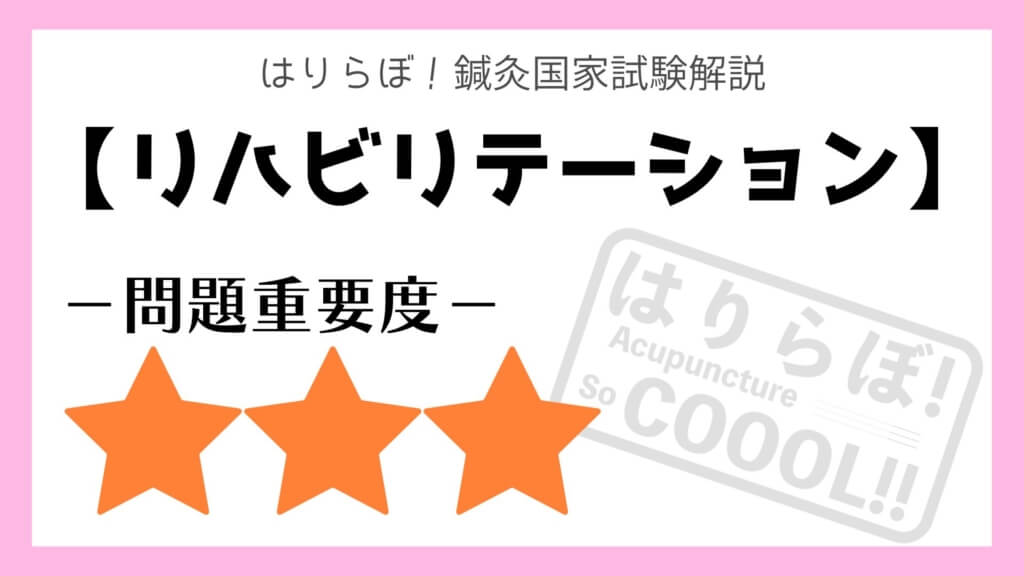
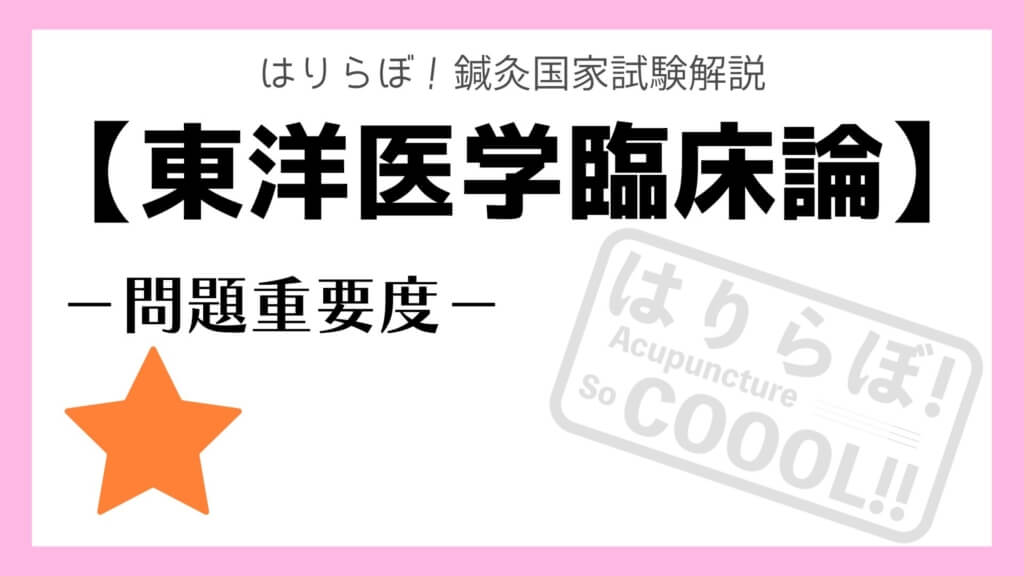
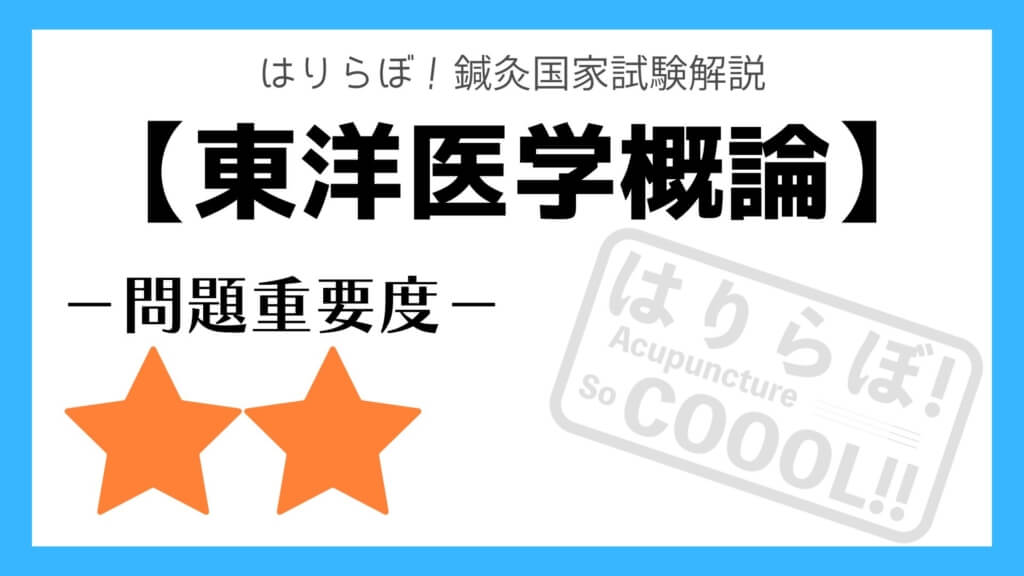
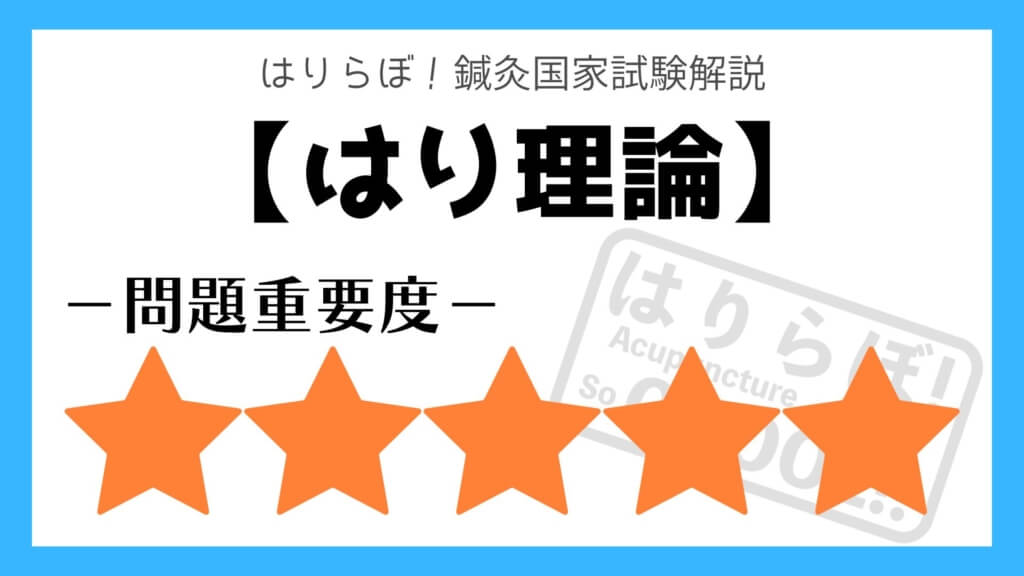
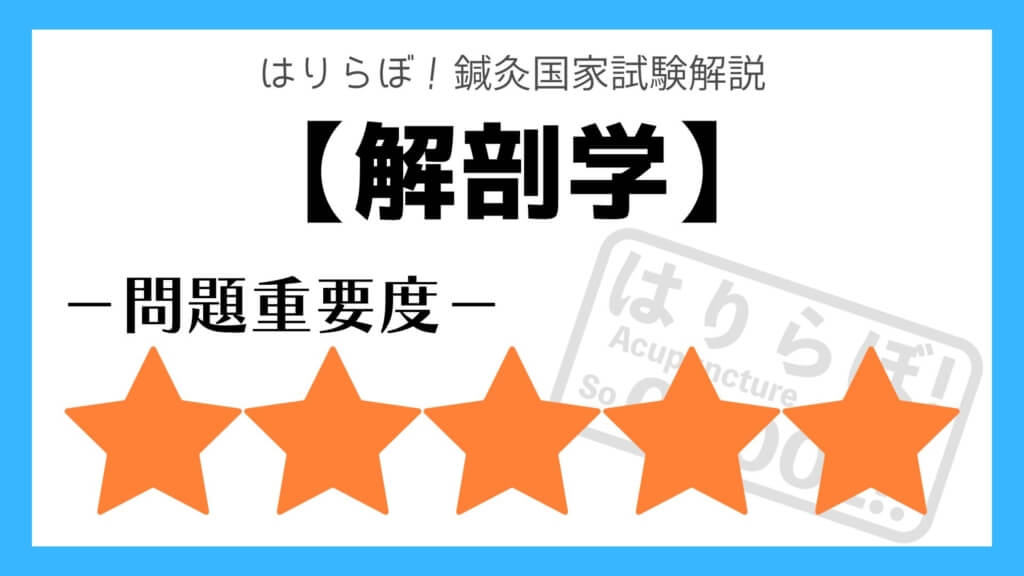
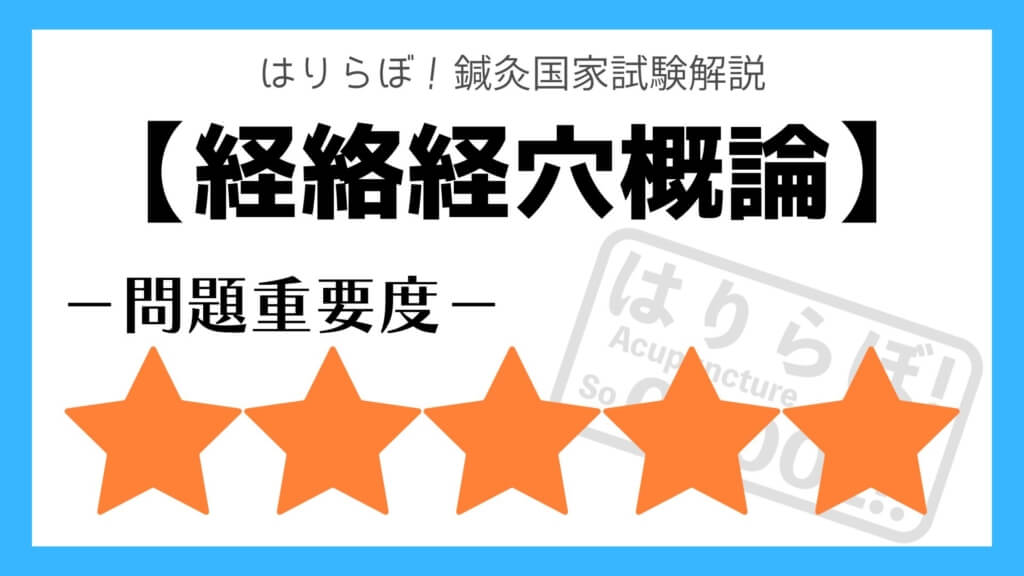
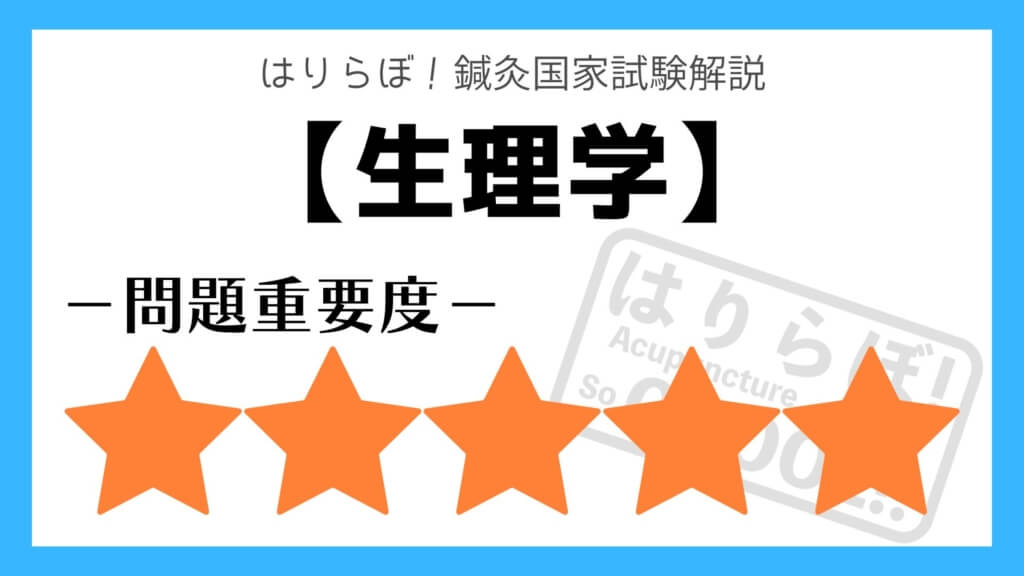
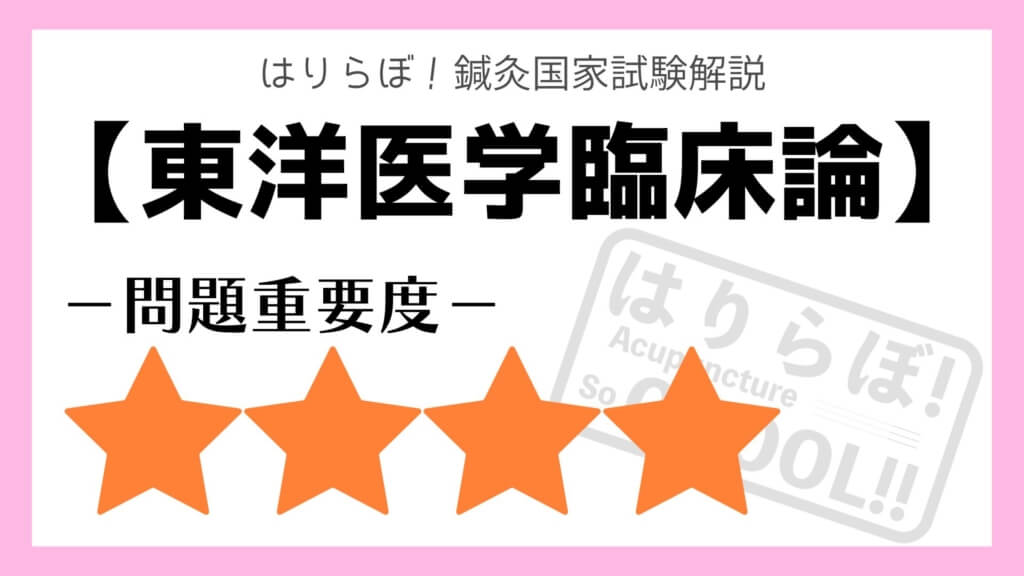
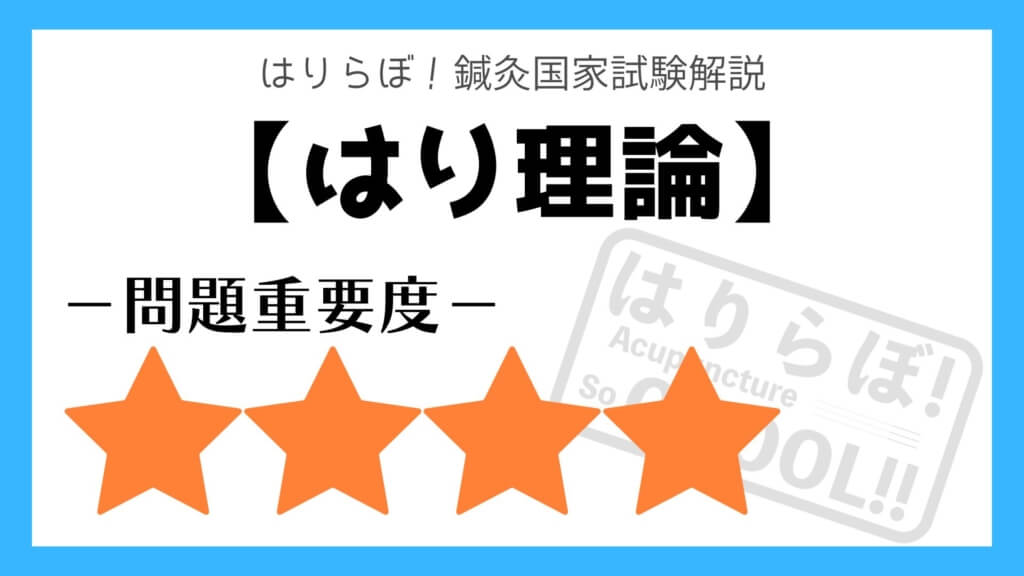

コメント