2回目の国家試験に向けて-生活リズム-
 よー
よー2回目の国家試験に向けて、4月からの勉強のサイクルを教えてもらってもいいですか。
 うーたん
うーたん学年の途中からアスレチックトレーナーコース(以下ATコース)がお昼から授業があり履修していたため、卒業しても1年間は学校に通わなければいけませんでした。
また卒後も夜間鍼灸の授業を受けていいよと言われていたので、午前中に仕事をしてお昼からATコースの勉強、その後夜間鍼灸の授業に参加できるときは参加すると言う形でした。
 よー
よー卒業したから勉強する環境がなくなった訳ではないんですね。
 うーたん
うーたんむしろ現役の時と変わらないような生活サイクルでしたね。
 よー
よーATコースを受講してなく、夜の授業だけ受けていいよとなっていた際、学校に通ってたと思いますか?
 うーたん
うーたん僕の場合は誰とでも仲良くなれると言うのがあって下のクラスにも遊びに行ったりしていて同じクラスになれたら楽しいなと思っていました。そんな中、実際同じクラスになれたのもあってすごい行くのが楽しかった。また下のクラスの担任の先生とも仲が良く、面倒を見てもらえていたので楽しみながら授業を受けれていました。
 よー
よーそれは現役の時の3年生よりも良い環境だったんですか?
 うーたん
うーたんそうですね。過去の試験内容などを書き出したりして、エンジニアの考え方を主軸に数字とかパーセンテージで◯%取れるとか、苦手科目の振り分けとかすごい細かく自分の中で分析もしました。
2回目の国家試験に向けて-勉強方法-
 よー
よーちなみに苦手な分野はなんですか?
 うーたん
うーたん解剖・生理ですかね。
途中から生理学ができるようになったおかげで臨床医学総論・各論の得点は少し上がりました。
 よー
よーこの解剖と生理学が苦手と言うのは3年生の頃から変わらないんですか?
 うーたん
うーたん基本的に1年から3年までずーっと苦手でした。
 よー
よー特に生理学が苦手となると、臨床系の科目がすごい大変かなと思うんですが、実際臨床系の科目の点数はどうでしたか?
 うーたん
うーたんはじめての国家試験結果で例えると6割位は得点していましたが、過去の問題をほぼ丸暗記で傾向として覚えていだからだと思います。
 よー
よー逆に得意な科目はありますか?
 うーたん
うーたん衛生とか丸暗記科目ですかね。
 よー
よー丸暗記科目とかは、確実に得点ができるような感じだったんですか?
 うーたん
うーたんそうですね。それは担任の先生もわかってたみたいで「君は暗記だけは得意だから経穴とかもちゃんとやれば覚えられるんじゃないか」と言われたりしました。それにプラスアルファ自分が好きな科目を勉強していました。
 よー
よー生理学のような理解する科目は苦手だったということですか?
 うーたん
うーたんそうですね。後は1年生から受けていた生理学の講義が丸暗記すれば、点数取れてしまうような内容だったのでそのままズルズル上がってきてしまったと言うのもありますかね。
 よー
よー理解する科目、特に生理学が理解出来るようになったおかげで臨床医学総論とか各論につながっていったとお話しされていましたが、理解される科目についてはどのように勉強されたのですか?
 うーたん
うーたん暗記と言うとやはり漢字練習帳みたいにひたすら書いて覚えるというのがあったのですが、ノート作り出したら意外と頭の中に入り始めたと言うのがありまして。以前は仕事をしていたりすることから一夜漬けで勉強していたりと、ノートを作る時間がなかった。
一度国家試験を受けて土台ができたところで、ある程度理解を深めたいとなった所でノートを作り始めて得点が安定してくるようになったと思います。
 よー
よーこのノートと言うのはどのようなノートを作られたのでしょうか?
 うーたん
うーたん普通にA4のノート2、3冊でそれぞれ解剖生理、東洋系、その他で分けて作っていました。
内容は、教科書が分厚すぎてそれをまとめるというのは苦手だったので、他の参考書とかで抜粋をする。特に表や図になっていて見やすいところを抜粋しました。その後、黒本とかを参照してプラスアルファ付け足した方がいいなという内容を細かく足してまとめ上げていく感じですね。
文字で書くというよりかは表とかフローチャート的な形で、頭の中で想像できるような形にしていました。
 よー
よーこれは1回目の国家試験に落ちてから作りはじめたものですか?
 うーたん
うーたん3年生の時もあったんですけど大した事なかったです。やはり2回目の国家試験の受験前に作った内容が濃かったです。
 よー
よーなにかこのノートを作るきっかけがあったんですか?
 うーたん
うーたん冊子を見ても、眺めているだけで頭の中に入らないという事が一つ。それから純粋に時間ができたからです。やはり仕事をしていた時に比べると、気持ち的な余裕が生まれたからかもしれません。
 よー
よーノートを作って行ったりする中で、苦手な科目を克服して受けた2回目の国家試験はどうでしたか?
 うーたん
うーたん前日のあん摩指圧マッサージの試験を解いて採点した時に「あー、今年簡単だなと思った。」実際に鍼を受けて得点は7割ぐらいでした。
 よー
よー今までのお話の中で勉強法として「ノートを作るという」一夜漬けではない勉強方法が加わりましたが、それ以外に何か変化した事はありますか?
 うーたん
うーたんATコースの授業があったので、解剖の筋骨格系や神経系等、整形外科疾患や検査法などに関しては勉強する機会に恵まれていたかもしれません。
 よー
よーちなみにこのトレーナーの試験対策はしていたんですか?
 うーたん
うーたんしていましたけど、まずは鍼の国家試験かなと。
結果的にATコースの試験対策が、鍼灸の国家試験の内容を一部フォローしていたと言う感じですかね。
 よー
よーATコースを受講していなかったとしたら、勉強していましたか?
 うーたん
うーたん解剖生理は苦手なママだったかもしれませんね。
もともとスポーツやっていたのもあってわかりやすかったのを覚えています。
改めて振り返って
 よー
よー学生生活振り返って「これをしたら落ちる」って事ありますか?
 うーたん
うーたん周りのモチベーションですかね。周りとどれだけ仲良くやっていられるか。一人ぼっちで勉強しているとなるとサポートもないし共有もできない。ちゃんと友達とか作っといた方がいいかなというのがあります。
あとは、先生との信頼関係も重要だと思います。先生も同じ人間なので、ばちばちしたりとか仲悪かったりするとフォローもされないというか、来づらくなるというのがありますかね。
 よー
よー自分とか周りのモチベーションはどのように維持されていたんですか?
 うーたん
うーたんご褒美制度にしていました。次の試験◯%超えたら、物をかったり遊びにいくなりみたいな形で調節していました。
人間関係重要ですね。笑
 よー
よー勉強についてだったらどうですか?
 うーたん
うーたん僕の場合は暗記が得意だったので、それらを理解しようとする意欲とか姿勢ですかね。
 よー
よー理解しようとする意欲とおっしゃられたのですが、ノートをつくりはじめたのって、この理解しようと思ったから作り始めたという事ですか?
 うーたん
うーたんそうですね。
 よー
よー以前までって暗記をするのが重要で、理解することを放棄されてたという感じなのでしょうか?
 うーたん
うーたん他の科目もあるじゃないですか。これを理解しようとしていると他の科目が間に合わないですし、理解するのを後回しにして逃げる感じですかね。時間も足りないし。
 よー
よー時間の余裕ができたから理解することに注力できたということですか?
 うーたん
うーたんそうですね。それが2回目の国家試験でした。
 よー
よー国家試験で重要だなと思う科目ありますか?
 うーたん
うーたん点数とれなかったのが、解剖生理でした。問題数を考えると解剖生理がある程度取れないといけないな。というのはありますよね。結局これらの科目が臨床科目につながるし、総合的な点数を上げるためには基礎が重要だという事ですね。
現に1回目の国家試験の時は、あと2点あれば鍼の試験も受かっていた。鍼が受かった人と成績を見比べた時に、学内での成績においては、最後は大差なかった。しかしそれまでの成績を比べた時に、受かっていた人たちは、それまでのテストでギリギリながらもボーダーには達していた人達でした。
 よー
よー睡眠時間はどうでしたか?
 うーたん
うーたんトータルで6時間は取っていました。12-2時ぐらいには寝て朝6時には起きる感じでしたね。途中で30分ぐらい寝たりをちょこちょこ繰り返す感じですかね。
 よー
よー国家試験の勉強に対して使っていた参考書やオススメの参考書はありますか?
 うーたん
うーたん黒本と国家試験の過去問が解けるネットサイトやアプリですね。
 よー
よー勉強する環境は重要ですか?
 うーたん
うーたんそうですね。とにかく勉強する環境はとても重要ですね。
 よー
よー最後に皆さんに伝えたい事はありますか?
 うーたん
うーたん勉強する時間の確保をしたほうがいい。実際、自分は作っていなくて心の余裕がなかった。3時間だけで変わると思います。
 よー
よー本日は長い間ありがとうございました!
インタビューを終えて
以上、うーたん先生への国家試験インタビュー全容となります。
うーたん先生はインタビュー中も真摯に向き合っていただき、当時の内容を鮮明にかつ丁寧な言葉で語って頂きました。
インタビューしていて感じた事は、
ダメならダメで次頑張ればいいというポジティブな印象が残っています。
実際の立場になった時に、割り切れるかというとそうではないと思います。
それが、うーたん先生を合格に導いた一つの要因なのかもしれませんね。
この場を借りて改めて感謝申し上げます。
うーたん先生、ありがとうございました。
自身の国家試験対策・勉強のモチベーション等に繋げて頂ければと思います。




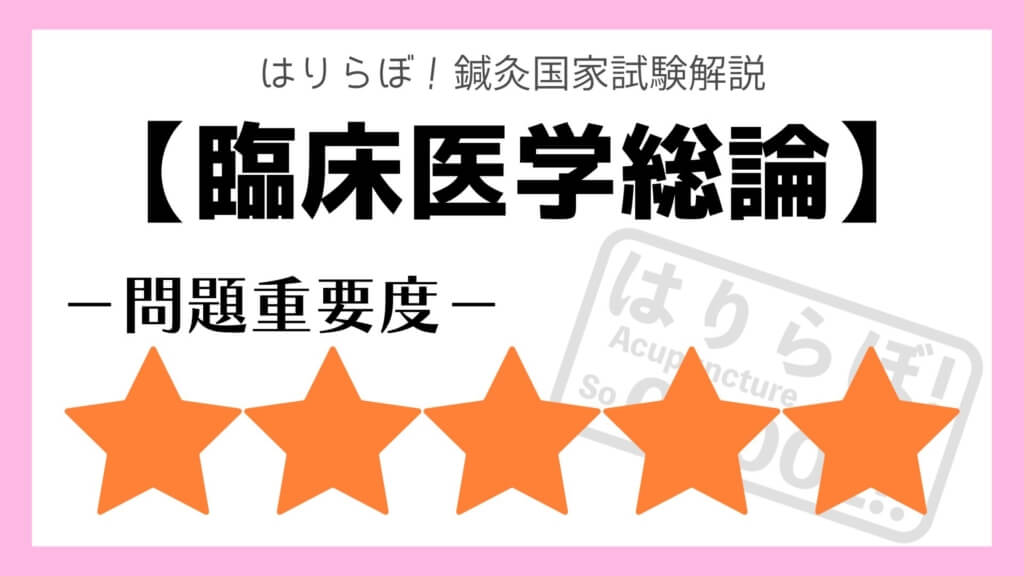
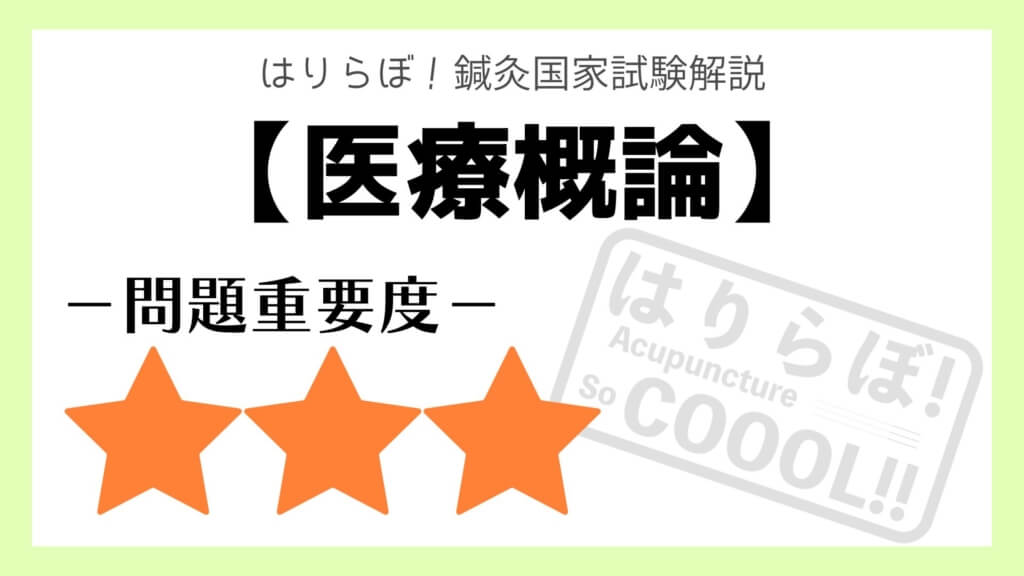
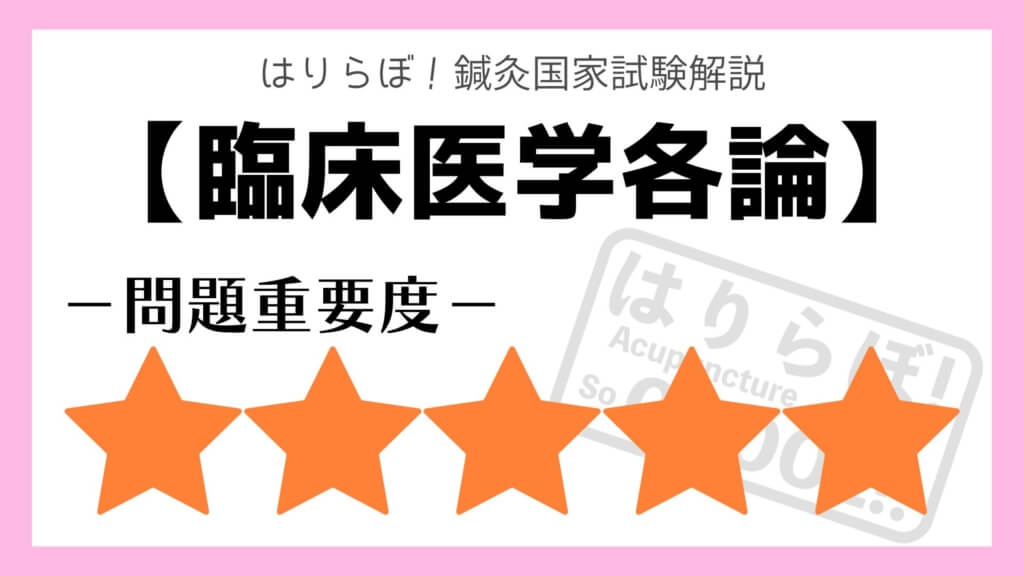
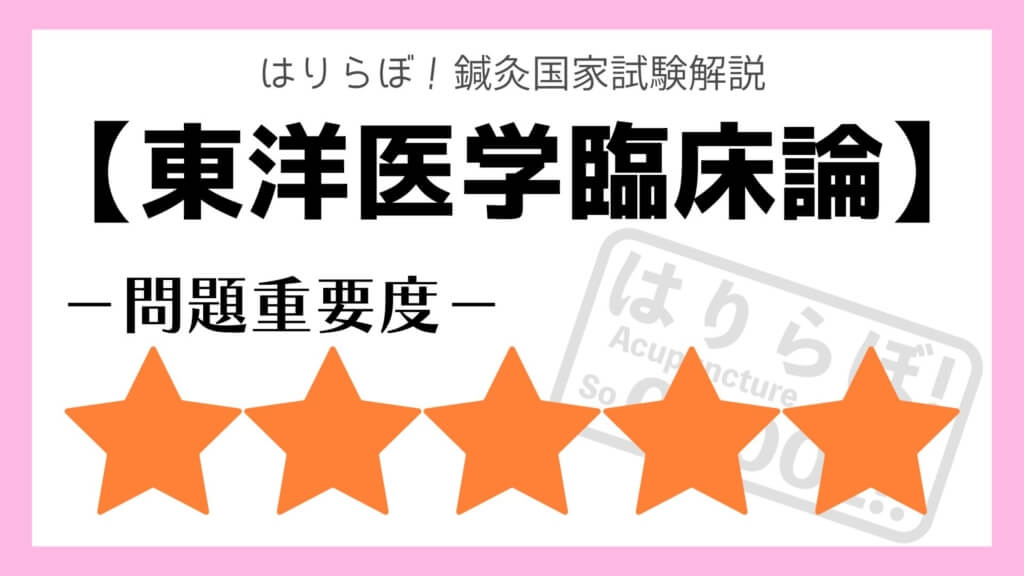
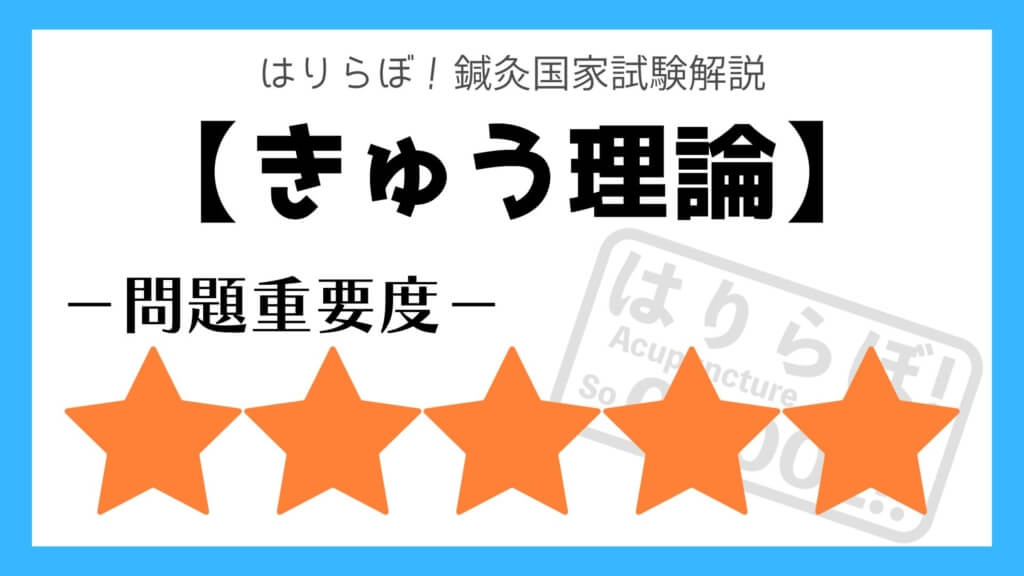
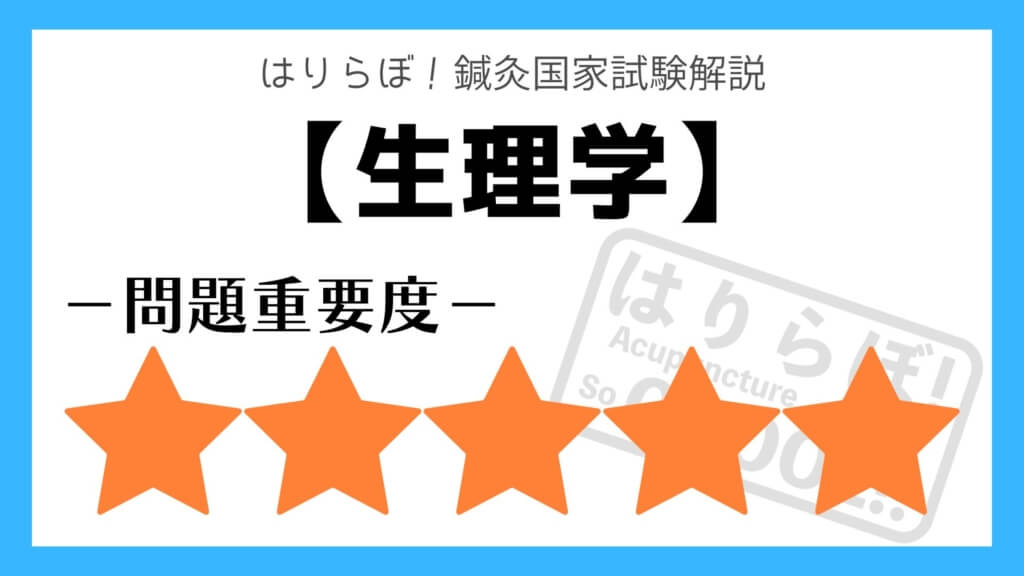
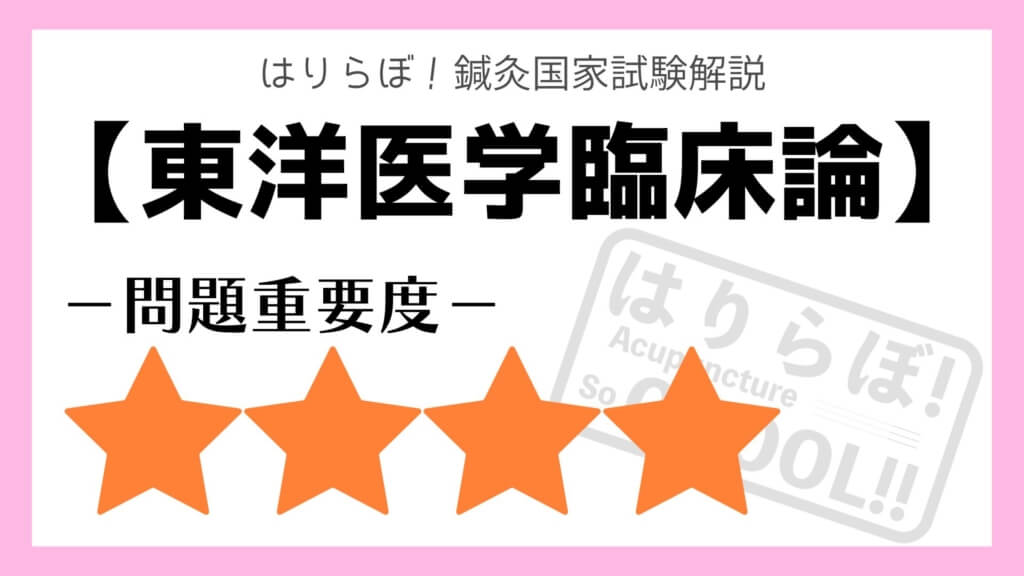
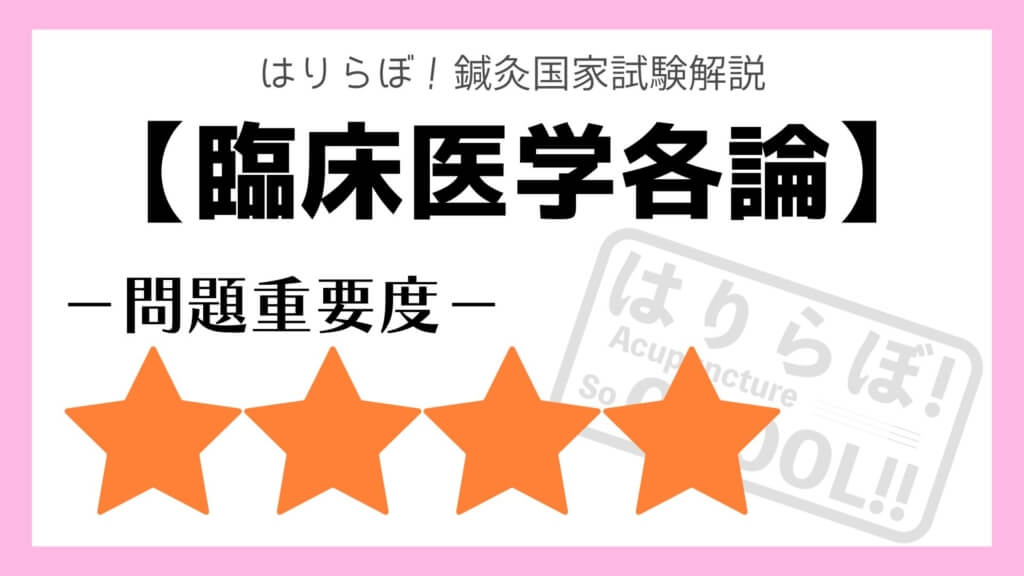

コメント