在宅鍼灸って知ってる?
HAMT=Home-visit Acupuncture and Moxibustion Therapist
代表:白石哲也氏により打ち出された、在宅鍼灸療法士育成プロジェクト。
今後、需要が高まるであろう在宅鍼灸の領域において、プロフェッショナルとして活動をする鍼灸師を育成する目的で活動している。
現在はnoteで¥1000-/月額で、これまでの100記事を超える在宅鍼灸に関する記事がで読み放題の『HAMT〜在宅鍼灸師のためのライブラリ〜』を提供している。

【対象】
主に在宅鍼灸師1−3年目の若手鍼灸師が対象。
内容としては治療院やトレーナー、ベテラン鍼灸師など様々な人でも非常に学びを深めることができるようなコンテンツ。【具体的なサービス内容】
白石氏noteより引用(一部表現を改変)
在宅における各分野のプロフェッショナルによって投稿される記事を読むことが出来る。
具体的な分野は下記となります。
⚫︎フィジカルアセスメント
⚫︎リスク管理
⚫︎経絡治療
⚫︎中医学
⚫︎泌尿器
⚫︎etc..
約3日に1度のペースで更新されるこのマガジン、在宅鍼灸の現場で活躍する鍼灸師たちや、専門分野のプロフェッショナルから生きた学びを得ることができるのはとても魅力である。
そんな魅力的なHAMTではあるが、本当に生きた学びを得られるのだろうか?
ということで、はりらぼ学生部の現役の鍼灸学生ライターが飛び出してHAMTの魅力をレポートしてきました!
※この記事はHAMTとはりらぼ!のタイアップ記事です。
・さえ
鍼灸学科2年生
高校時代腰痛の治療を受けたことをきっかけに鍼灸を学びたいと思うように。今は鍼灸の機械的刺激・温熱刺激が症状の改善に影響を及ぼすことに面白さを感じている。
どの科目も好きだが、特に東洋医学の考え方をもっと知りたい。
犬派。
・りさこ
鍼灸学科2年生
レディース鍼灸やメンタルケアなど幅広く人に寄り添える鍼灸の魅力に惹かれて鍼灸師を目指すように。
旅行と猫が好き。
◎患者さんが腕や手の痺れを訴えてきた時、あなたならどうやって推理しますか?
 さえ
さえ私が高校生の頃、同じ部活の友達が胸郭出口症候群になったことがありました。
手の痺れにずっと悩まされていたのがとても印象に残っています。
 おかし
おかし胸郭出口症候群でみられる症状のひとつだね。
 さえ
さえ大学に入り、手の痺れが症状として出る疾患や障害は本当にたくさんの種類があることを知りました。
手の痺れは日常生活にも支障をきたすし、感じたらすぐ相談しに鍼灸院などに行く人も多いと思います。
 おかし
おかし日常生活に支障をきたすことが多いから鍼灸院ではよく見られるけど、実際、判断できるかな…
 さえ
さえさまざまな疾患で出る症状だからこそ!その原因が何なのかを正しく推察できないと根本から治すことはできないので、推理の仕方を練習するのは大切だなと感じています。
 おかし
おかし確かに!そうだよね!
 さえ
さえこちらの記事では、はじめに腕や手の痺れを訴える70代の女性が紹介され、どんな疾患が思い浮かびますか?という問いかけがあります。
 おかし
おかしうんうん
 さえ
さえ私たちは実際にその患者さんと向き合っているわけではないので、詳しく聞いたりして絞り込むことはできませんが、シンキングタイムのうちにたくさん思い浮かべて候補を挙げておくことは実際の問診の時でもとても大切なことだと思うので、この体験だけでも良い経験になると思いました。
 おかし
おかしたくさんの可能性(候補)を出せることを大切だね!
 さえ
さえそして次に、たくさん思い浮かべた例の中から絞っていく手段として、『OPQRST』が示されます。
 おかし
おかしOPQRSTとは?
 さえ
さえOPQRSTとは、その症状が、いつから・どこが・どのように・どのあたりまで・どれくらいの強さで・どの程度の時間続いているのかを掘り下げる上で役に立つキーワードなので、今後新しい疾患や障害を習った時、想像上の患者さんの『OPQRST』を考えてみるのも楽しそうな学び方だなと思いました。
 おかし
おかしなるほど!OPQRSTを覚えておくと、患者さんの状態が想像しやすいね!
 さえ
さえ以降の部分では、『OPQRST』を用いて絞り込んだところからさらに絞り込んで特定する方法が述べられています。
また、手の痺れと言われると、運動器系の疾患を思い浮かべそうなのですが、必ずチェックしておかなければならない緊急性の高い血管系の疾患についても学べます。
 おかし
おかし手のしびれでも緊急性の高い疾患の発見に繋がったりするからチェックしなきゃ!
 さえ
さえ鍼灸師として適応を見極めることは大切なことだと思うし、手の痺れを訴える人もたくさんいると思うので、「手の痺れ」についてもう一度見直したい方にとてもおすすめの記事です。
 おかし
おかしぜひ!記事を読んでしびれについて見直してみよう!
◯潤いを充実させるメリット
 おかし
おかし今回はどんな記事を読んできたのかな?
 りさこ
りさこ今回の記事は以前から読んでいたのぶさんの潤いシリーズの4つ目の記事です!
 おかし
おかし潤いシリーズの4つ目か!
 りさこ
りさこ以前から読ませていただいている流れで読み始めたところ、やはりとても面白い内容だったので是非紹介したくなりこちらの記事を選びました。
 おかし
おかしどんな内容だったのかな?
 りさこ
りさこ記事では、潤いが充実すると得られる効果として美容効果、姿勢改善、呼吸効率アップ、消化吸収効率アップ、トレーニング効果アップ、全身の循環が改善、デトックス効果、アンチエイジング効果の8つの効果が挙げられていて、それぞれ効果があらわれる理由が解説されていました。
 おかし
おかし潤いが充実しているといいことだらけだな…
 りさこ
りさここれらの効果は全てとても興味深いのですが、この中でも私が特に面白いと感じたのは、自分ではあまり想像つかなかった、そして現に今私が気にしている姿勢改善です。
 おかし
おかし確かに、潤いで何故姿勢改善なんだろう?
 りさこ
りさこ姿勢改善になぜ効果があるのかというと、姿勢維持筋のなかでも五臓と大きく関係しているのが「横隔膜」であり、その横隔膜の柔軟性を支えているのが「潤い」だからだそうです。
 おかし
おかし横隔膜の柔軟性を支えるのが潤いなのか!
 りさこ
りさこ横隔膜は腰椎部は第1-4腰椎(椎体)、肋骨部は第7-12肋軟骨の内面、胸骨部は胸骨(剣状突起)一部は腹横筋腱膜の内面に起始しており、腱中心に停止しています。
のぶさんによると、このうち腰椎に起始していることがポイントだそうです。
 おかし
おかしうんうん
 りさこ
りさこたしかに、横隔膜は息を吸うときに収縮し、息を吐くときに弛緩しているのでここで弛緩が出来ないと腰椎にストレスがかかり骨盤の傾きや偏位、脊柱のアーチが崩れることにつながるという理由に納得がいきました。
 おかし
おかし姿勢が悪いと呼吸もしにくいから、解剖学的に見ていくと確かに横隔膜の柔軟性って大切だね
 りさこ
りさこ皆さんも是非気になる効果の解説を読んでみてください!美容に興味がある方、トレーニングしている方など幅広い皆さんにお勧めしたい記事でした。
HAMTに興味をもったら
高齢化社会が進む今、訪問鍼灸領域はますます需要が伸びていくことが想定される。
鍼灸師として幅広いフィールドで活躍するためにも、今のうちに知識と視点が広がるこれまでの100記事を超える在宅鍼灸に関する記事がで読み放題の『HAMT〜在宅鍼灸師のためのライブラリ〜』に登録してみてはいかがだろうか。

| お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 白石哲也 | @physio_tetsuya |

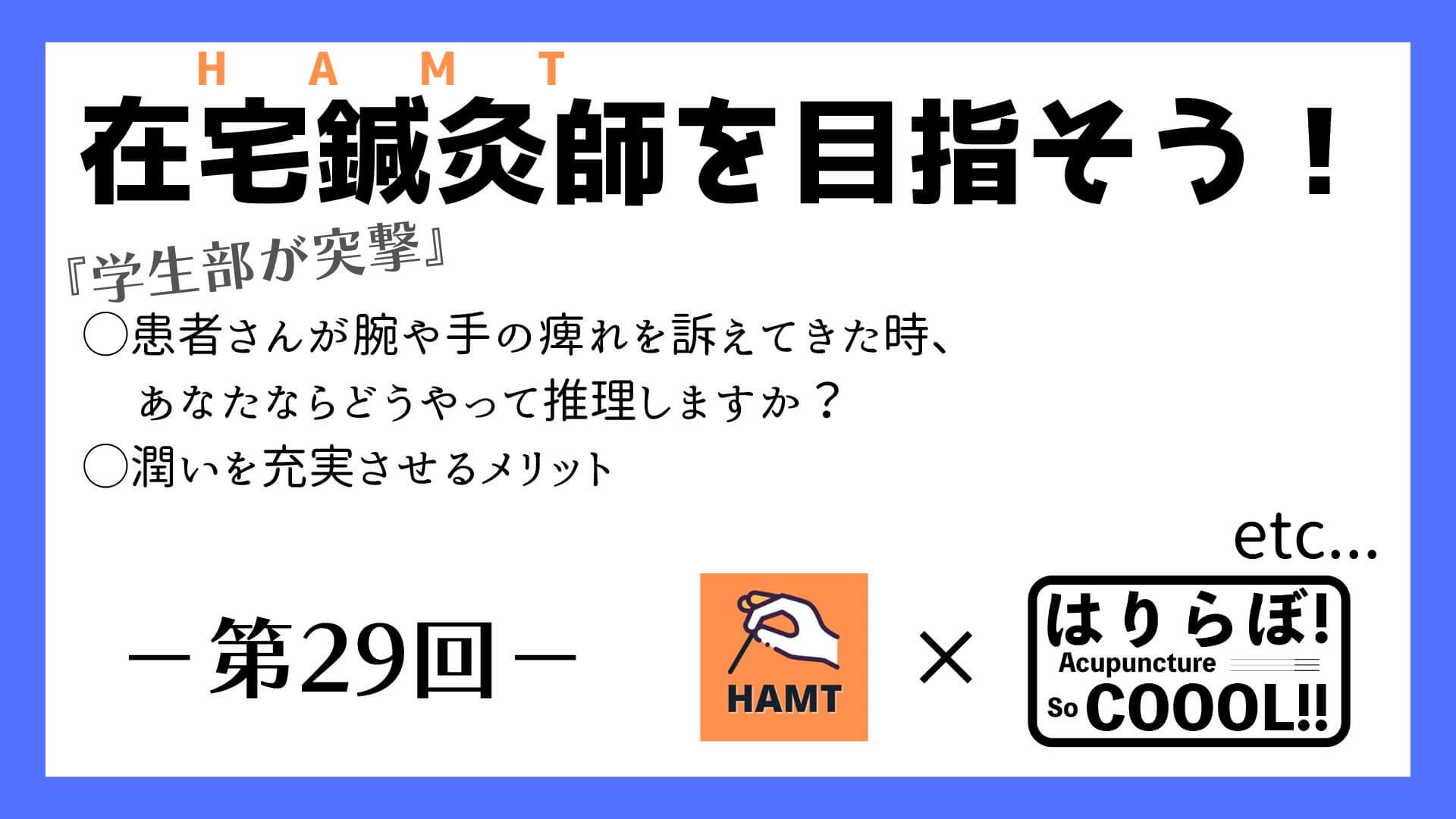


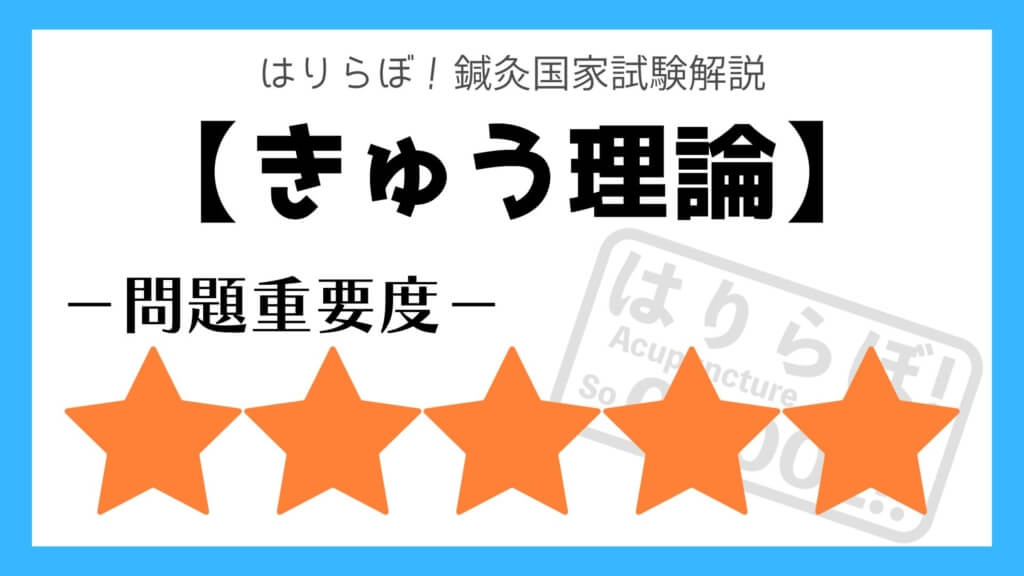
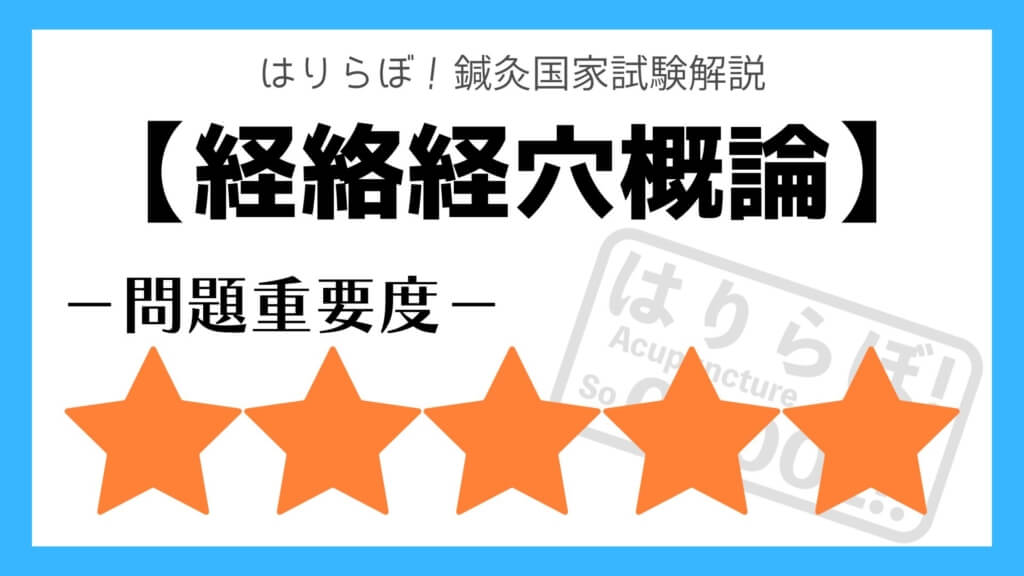
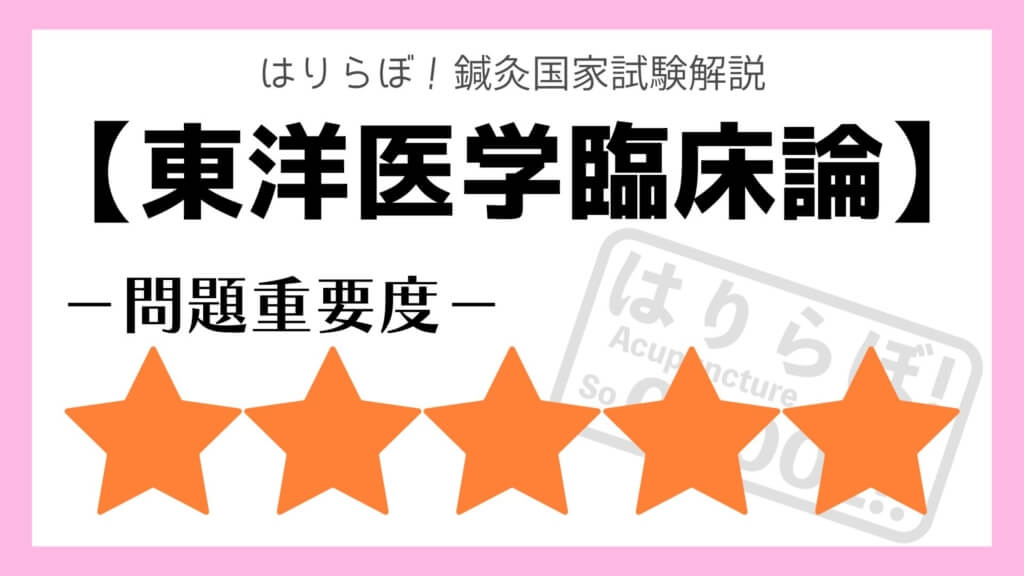

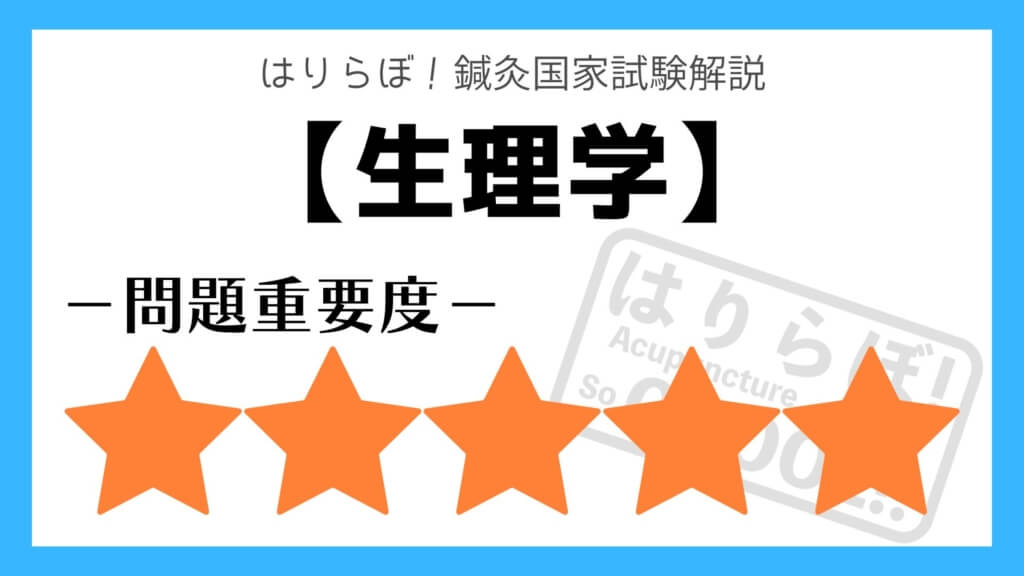
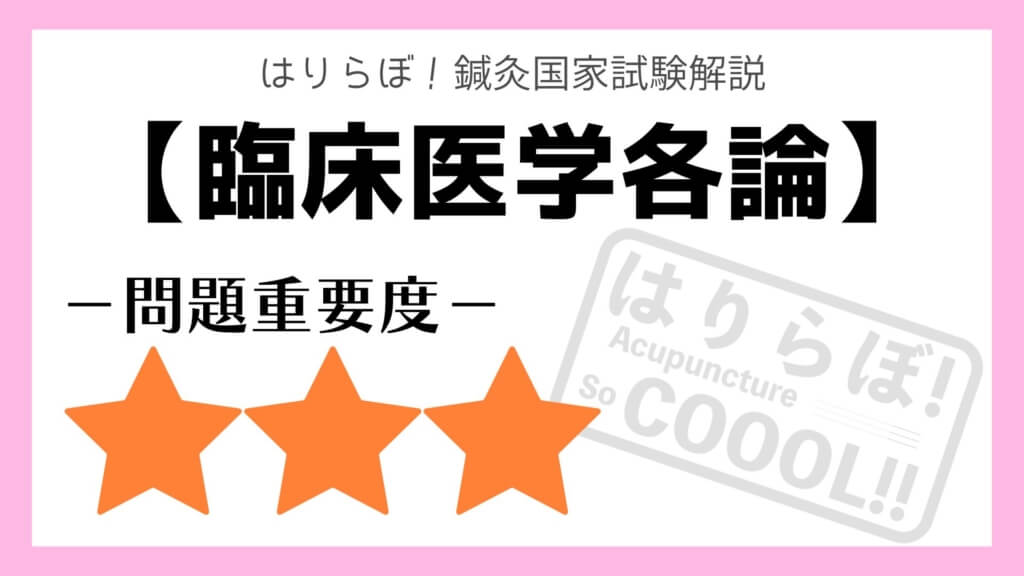
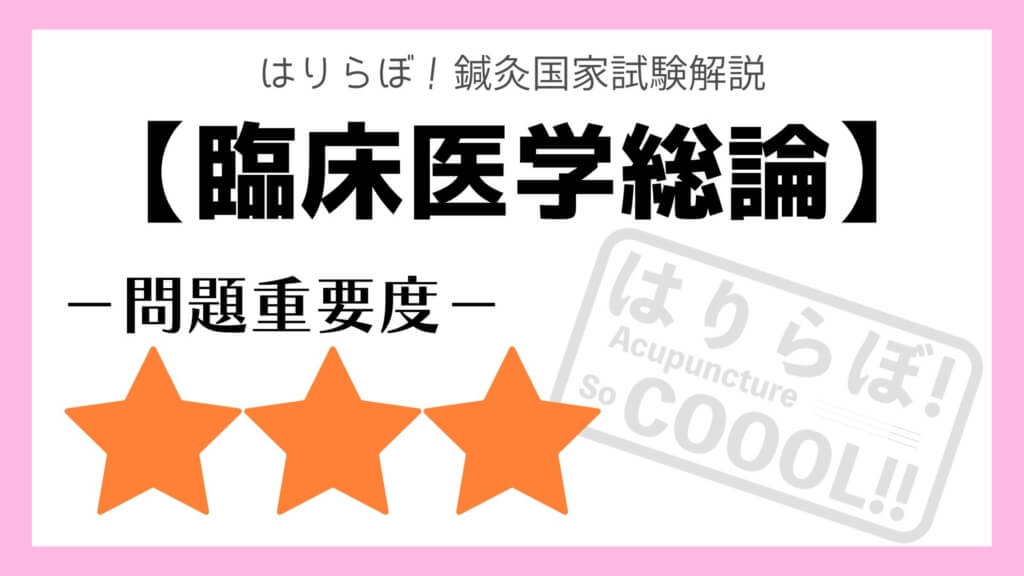
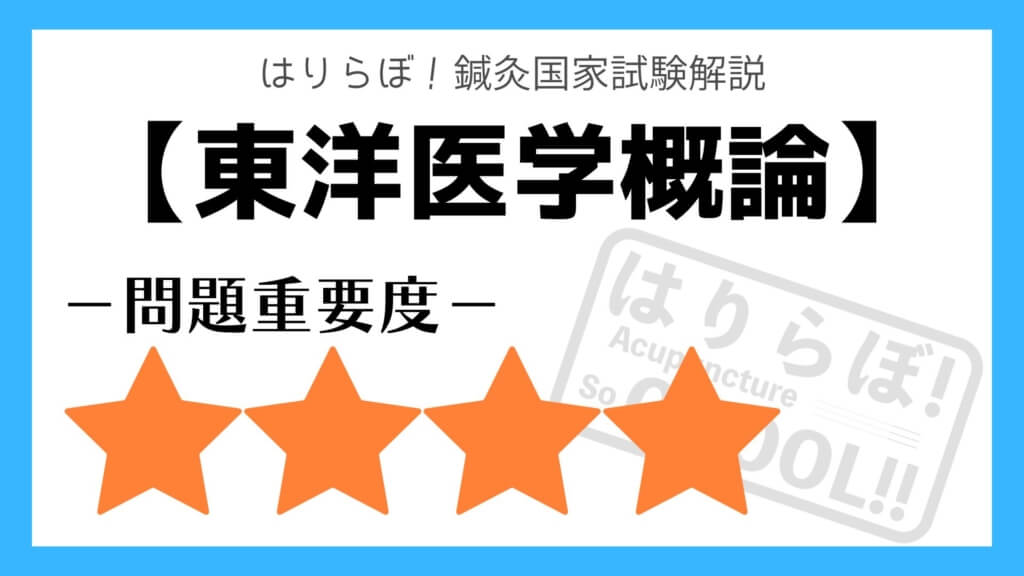
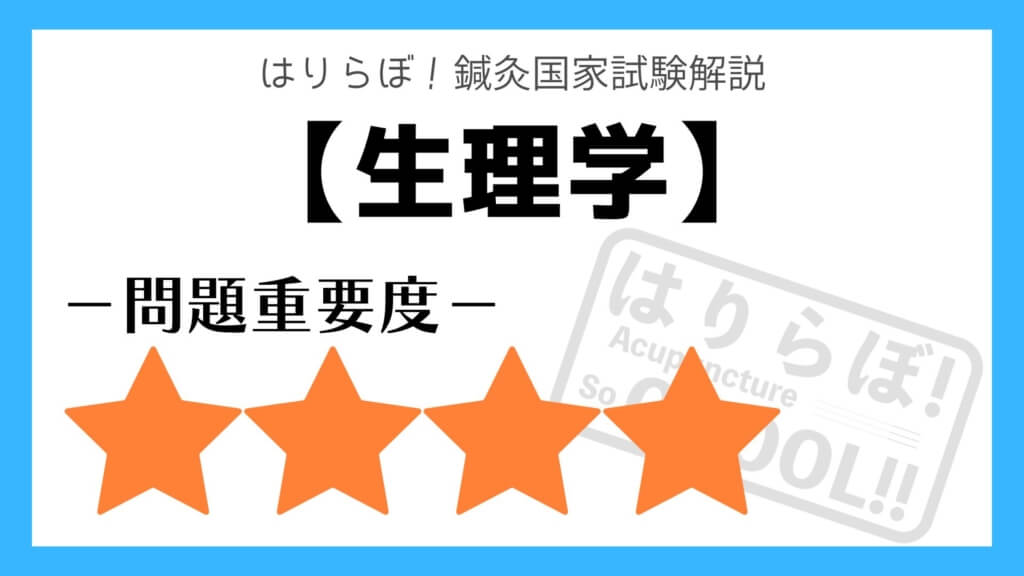

コメント