在宅鍼灸って知ってる?
HAMT=Home-visit Acupuncture and Moxibustion Therapist
代表:白石哲也氏により打ち出された、在宅鍼灸療法士育成プロジェクト。
今後、需要が高まるであろう在宅鍼灸の領域において、プロフェッショナルとして活動をする鍼灸師を育成する目的で活動している。
現在はnoteで¥1000-/月額で、これまでの100記事を超える在宅鍼灸に関する記事がで読み放題の『HAMT〜在宅鍼灸師のためのライブラリ〜』を提供している。

【対象】
主に在宅鍼灸師1−3年目の若手鍼灸師が対象。
内容としては治療院やトレーナー、ベテラン鍼灸師など様々な人でも非常に学びを深めることができるようなコンテンツ。【具体的なサービス内容】
白石氏noteより引用(一部表現を改変)
在宅における各分野のプロフェッショナルによって投稿される記事を読むことが出来る。
具体的な分野は下記となります。
⚫︎フィジカルアセスメント
⚫︎リスク管理
⚫︎経絡治療
⚫︎中医学
⚫︎泌尿器
⚫︎etc..
約3日に1度のペースで更新されるこのマガジン、在宅鍼灸の現場で活躍する鍼灸師たちや、専門分野のプロフェッショナルから生きた学びを得ることができるのはとても魅力である。
そんな魅力的なHAMTではあるが、本当に生きた学びを得られるのだろうか?
ということで、はりらぼ学生部の現役の鍼灸学生ライターが飛び出してHAMTの魅力をレポートしてきました!
※この記事はHAMTとはりらぼ!のタイアップ記事です。
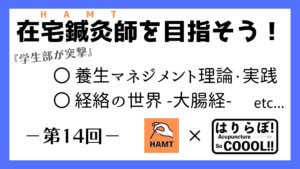
・まりな
鍼灸学科4年生
千葉県出身で好きな食べ物はさつまいも。好きな科目は生理学。
鍼灸が薬を用いない治療であることや、体に作用する不思議さに興味を持ち、鍼灸師を目指すように。
・かいと
鍼灸学科3年生
興味がある分野は中医学・東洋医学。
鍼灸師を目指した理由は鍼灸は学ぶに連れて西洋医学的・東洋医学的2つの面からアプローチできる鍼灸の魅力に引き込まれたから。
好きなことはテニス、音楽を聴くこと。
○腎が弱った時に注意することをまとめてみた
 まりな
まりな今回はタイトルの通り”腎”に対する情報が盛りだくさんの記事でした!
 おかし
おかし今回の記事は”腎”に関してだね!どんな記事だったのかな?
 まりな
まりなまず、日常生活での腎が弱っている時の症状とその養生方法について紹介されています。腎は、耳、足腰、尿などに関係して症状が出てくる臓だと簡単に考えていましたが、それ以外にも腎を傷めた時の症状は多く紹介されていました!
 おかし
おかし自分は腎が弱いから、養生方法は知りたいな!耳や足腰、尿以外にも腎を傷めた時の症状についても気になるな!
 まりな
まりな養生例には、”耳を疲れさせない”、”足腰への刺激”、”水様性の下痢、頻尿、多尿がないか確認する”などが紹介されていました。
 おかし
おかしうんうん
 まりな
まりな腎は内向きのエネルギーを欲しており、”守備力”を上げることがカギとなるそうです! また、腎が弱っているときに六邪が入ってきた際の症状についても説明してくれています。
 おかし
おかし腎が弱っている時に六邪が入ってきた際の症状とは?
 まりな
まりな風邪では津液が乾いてしまい、虚熱が発生し、さらに慢性化によりその虚熱が減少して冷えの症状として出てくるということも書いてありました。教科書では虚熱の症状までしかチェックしていなかったので、実際に慢性化するとむしろ冷えが出るという点が面白いなと感じました。
 おかし
おかしなるほど!慢性化すると冷えが出るのはそういった流れがあって出てくるのか!
 まりな
まりななので、腎はまさに”縁の下の力持ち”だなと感じました。特に東洋医学の五行学説に関係するものが多くあるので、五行の分類も合わせて覚えるといいですよね。
 おかし
おかし東洋医学の復習にもなるし、新しい発見もできそうだね!
 まりな
まりなそして、腎は湿との関係も深い臓ですよね。そんな水が停滞して起こる”水気病”の症状と養生例についても記事での確認ポイントかなと思いました。
 おかし
おかし腎と湿は東洋医学でも重要なポイントだよね!”水気病”も確認ポイントになるのか!
 まりな
まりなさらに興味深かったのは、腎と命門の関係についてです。腎と命門は私の中で繋がりがあまりなかったのですが、心包の陽気が太陽膀胱経、少陰腎経、右腎、命門へ通るまでの図を見て、腎が寒邪に侵された時=太陽経の陽気が損なわれたという意味がとても理解しやすかったです。
 おかし
おかし命門といえば経絡経穴!そこまで関連した内容になっているのか!
 まりな
まりな私自身、1・2年生の頃は、友達と体の状態について五行を用いて診断するという事をしていたのですが、大学での学年が上がるにつれて、模試などが増え、東洋医学は単語で覚えるようになってしまっていました。
 おかし
おかしうんうん
 まりな
まりなのぶさんや他のライターさんの記事からも、このように東洋医学的に患者さんを診る際に参考になる内容を学ぶことができ、西洋医学だけでなく多面的に見る必要性に気づかせていただきました!
 おかし
おかし多面的に患者さんを診ることができるようになるために記事をチェックしなきゃね!
○これから在宅鍼灸師として働きたい人が押さえておきたいフィジカルアセスメント3つのポイント
 おかし
おかし在宅鍼灸師として働くためのフィジカルアセスメント!ここまで特化した内容は学ぶことは少ないよね。
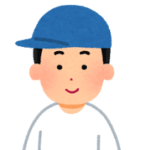 かいと
かいとはい。記事の冒頭にもあるように、学校では在宅分野について学ぶことは少ないです。
 おかし
おかしうんうん
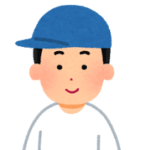 かいと
かいとだからこそ、学生のうちに知っていたら強みになるんだ!と思い、僕と同じ在宅分野について詳しく無い人にも知ってほしいと思い、書きました!
 おかし
おかしお!そこまで言われるとどんな記事か気になるな!
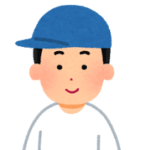 かいと
かいと今回の記事では、在宅鍼灸をやる上での重要な3つのポイントがてっちゃん自身の経験を踏まえた例と一緒に紹介されています。その中でも、2つ目のポイントである【個別のリスク管理リストしておく】これがとても参考になりました!
 おかし
おかし3つのポイントでも【個別のリスク管理リストしておく】が参考になったんだね!
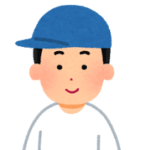 かいと
かいとそうなんです!各患者さんに対してのリスク管理を頭の中で考えて行動するというのは臨床経験の無い僕はやったこともないので、急に在宅鍼灸師として現場に出されてもできないんじゃないか、、と前々から不安に感じていました。
 おかし
おかし何事もはじめは不安になることはあるよね。リスク管理は特に!
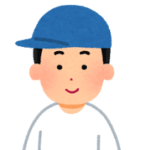 かいと
かいとですが、記事を読んで、リストを作ればその場で確認できるため、ミスも減るし、他の他職種の人とも連携が取りやすく、むしろ頭で行うよりリスト化の方が良いんじゃないか!と感じました。
 おかし
おかし自分の整理だけじゃなくて他職種との連携も考える。在宅では重要なことだね!
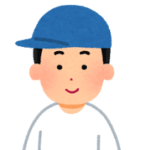 かいと
かいとはい!リスク管理は在宅分野では必須のものだと思うので、症状に対しての考えられる疾患であったり、薬に対しての副作用であったりなどを学生である今のうちからリスト化しておくと実際に現場に出た時に生きてくるのでは無いかと感じました!
 おかし
おかし現場に出る前から準備をしておく。そのためには記事を読まなきゃね!
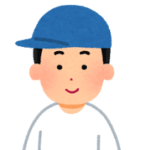 かいと
かいと具体的なリスク管理のリストを作ればいいのか、他の2つのポイントとは何なのかというのは是非記事を読んで確認してください!
HAMTに興味をもったら
高齢化社会が進む今、訪問鍼灸領域はますます需要が伸びていくことが想定される。
鍼灸師として幅広いフィールドで活躍するためにも、今のうちに知識と視点が広がるこれまでの100記事を超える在宅鍼灸に関する記事がで読み放題の『HAMT〜在宅鍼灸師のためのライブラリ〜』に登録してみてはいかがだろうか。

| お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 白石哲也 | @physio_tetsuya |

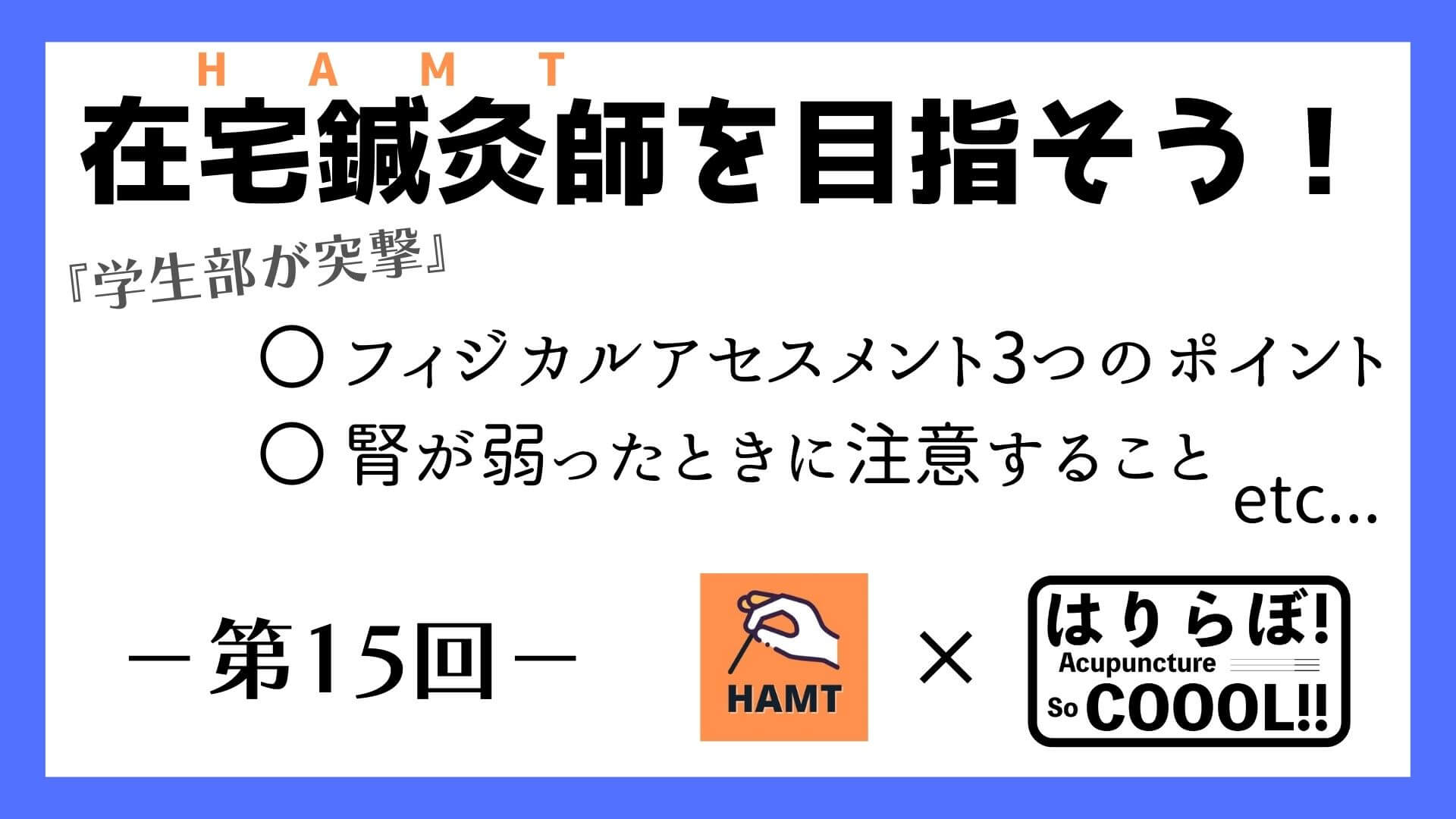


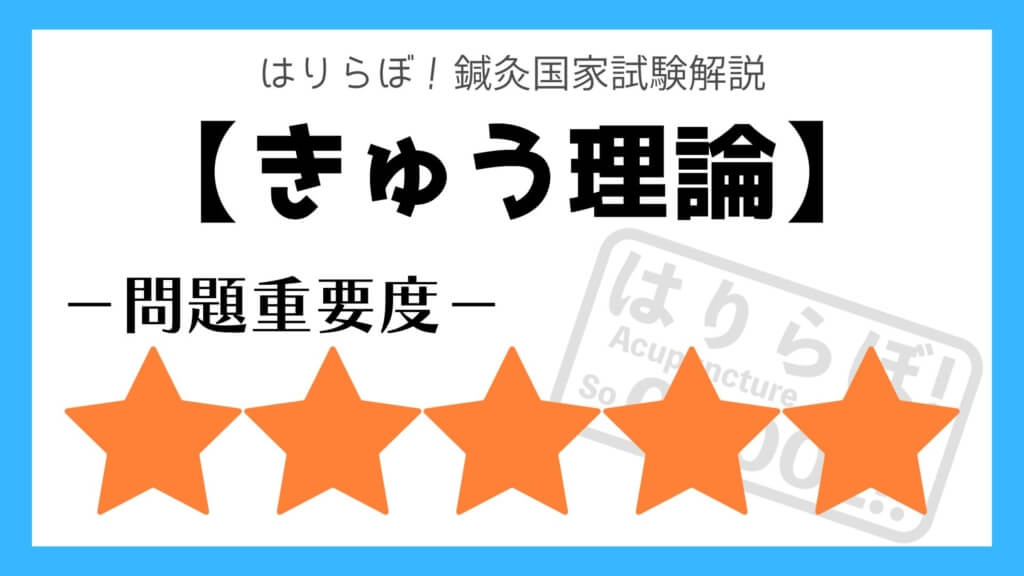
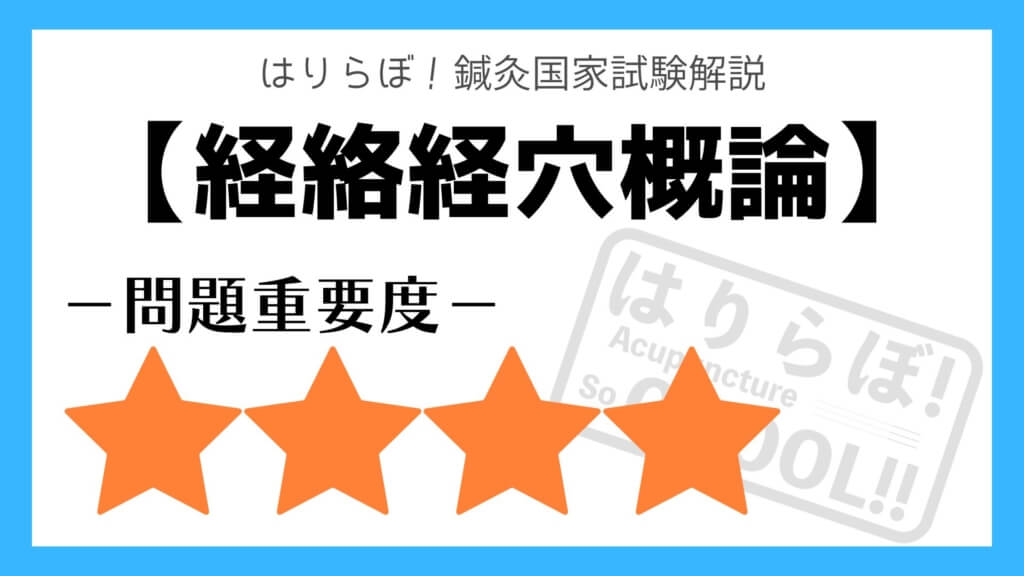
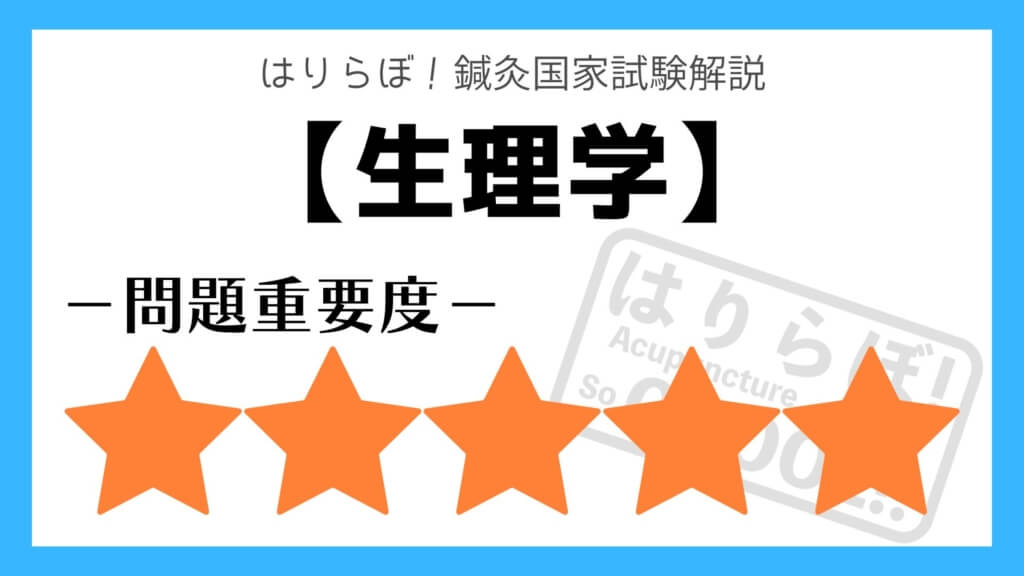
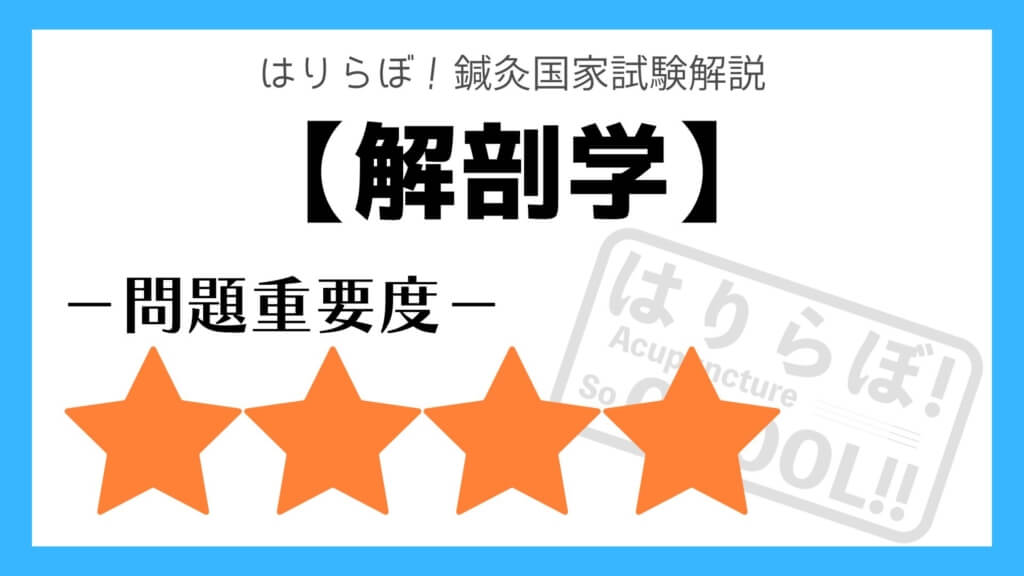
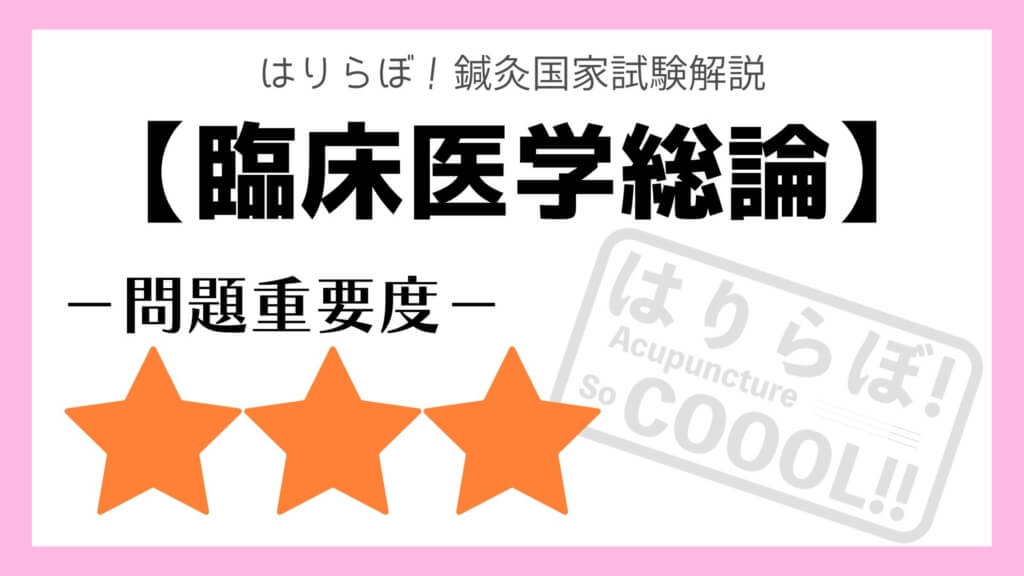
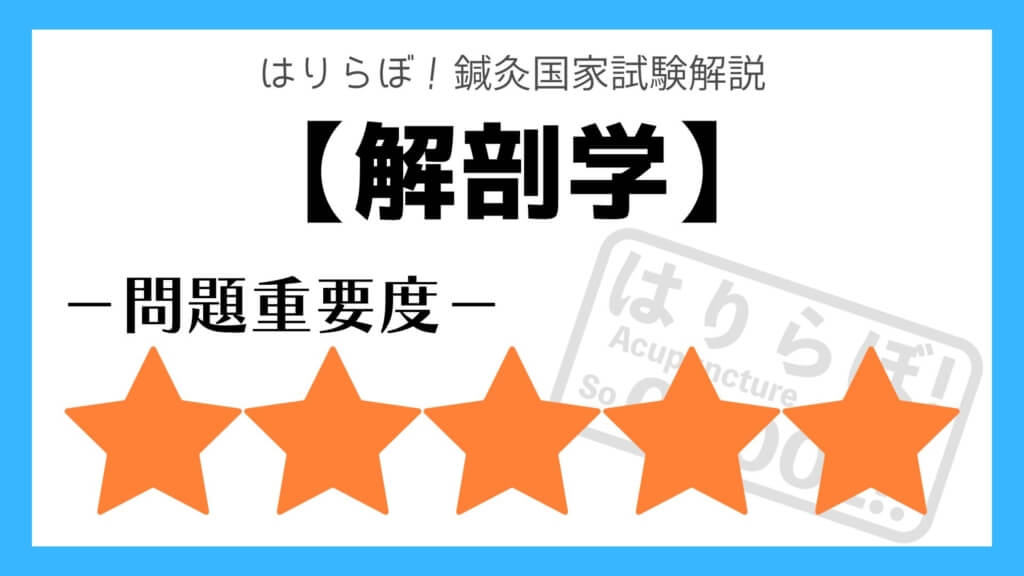
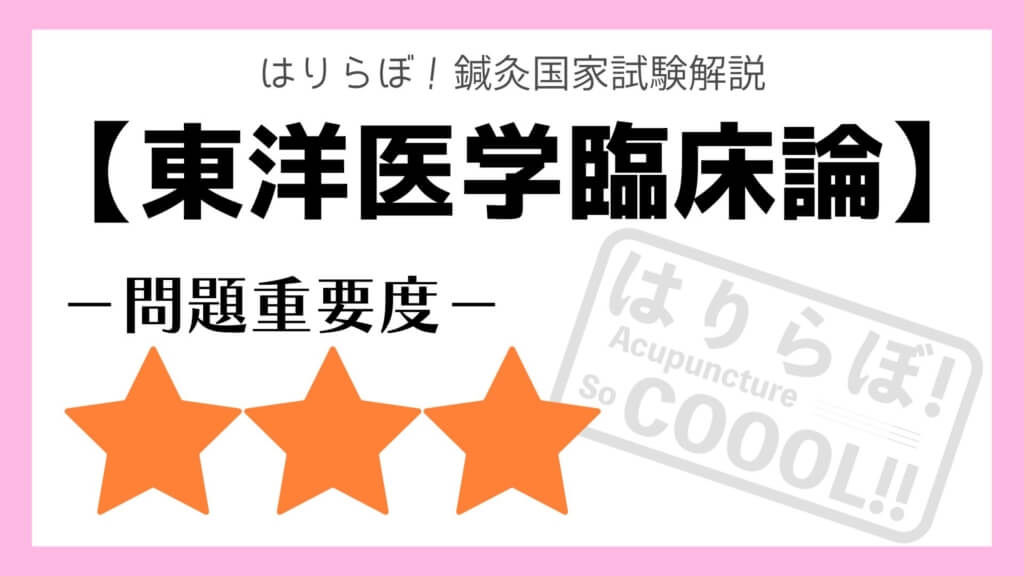
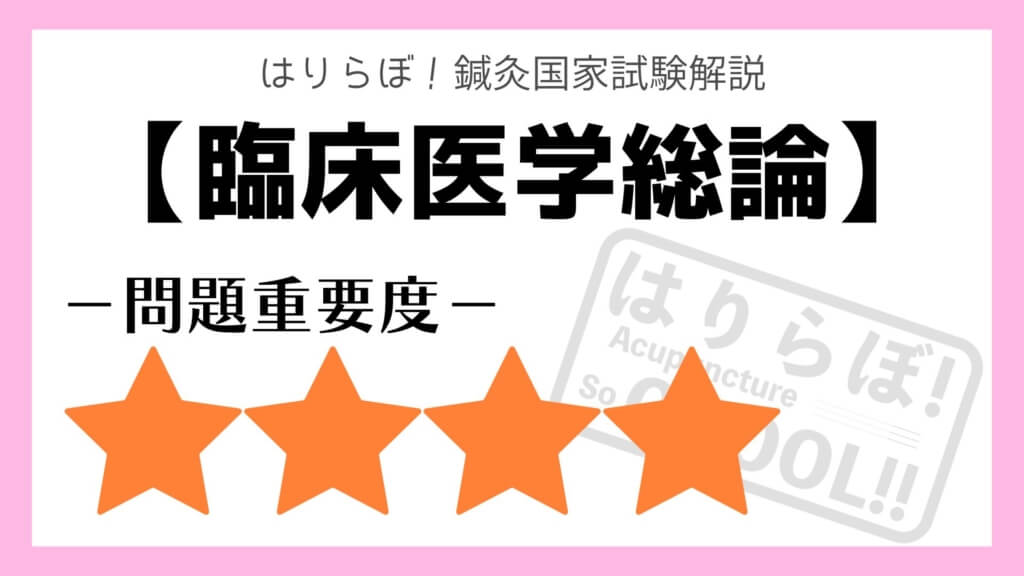
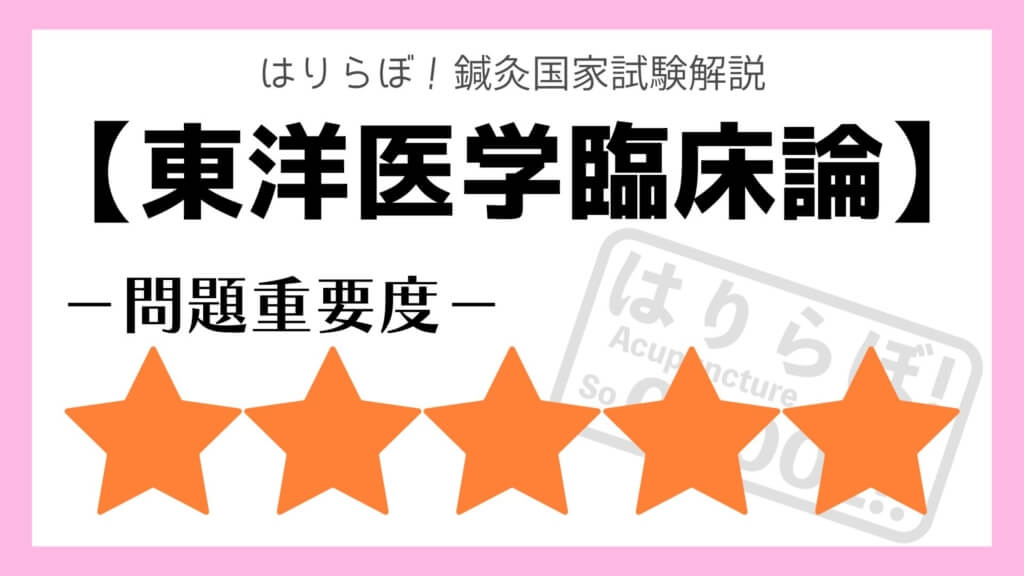

コメント