在宅鍼灸って知ってる?
HAMT=Home-visit Acupuncture and Moxibustion Therapist
代表:白石哲也氏により打ち出された、在宅鍼灸療法士育成プロジェクト。
今後、需要が高まるであろう在宅鍼灸の領域において、プロフェッショナルとして活動をする鍼灸師を育成する目的で活動している。
現在はnoteで¥1000-/月額で、これまでの100記事を超える在宅鍼灸に関する記事がで読み放題の『HAMT〜在宅鍼灸師のためのライブラリ〜』を提供している。

【対象】
主に在宅鍼灸師1−3年目の若手鍼灸師が対象。
内容としては治療院やトレーナー、ベテラン鍼灸師など様々な人でも非常に学びを深めることができるようなコンテンツ。【具体的なサービス内容】
白石氏noteより引用(一部表現を改変)
在宅における各分野のプロフェッショナルによって投稿される記事を読むことが出来る。
具体的な分野は下記となります。
⚫︎フィジカルアセスメント
⚫︎リスク管理
⚫︎経絡治療
⚫︎中医学
⚫︎泌尿器
⚫︎etc..
約3日に1度のペースで更新されるこのマガジン、在宅鍼灸の現場で活躍する鍼灸師たちや、専門分野のプロフェッショナルから生きた学びを得ることができるのはとても魅力である。
そんな魅力的なHAMTではあるが、本当に生きた学びを得られるのだろうか?
ということで、はりらぼ学生部の現役の鍼灸学生ライターが飛び出してHAMTの魅力をレポートしてきました!
※この記事はHAMTとはりらぼ!のタイアップ記事です。
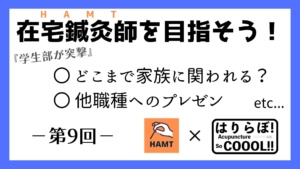
- まりな
鍼灸学科3年生
千葉県出身で好きな食べ物はさつまいも。好きな科目は生理学。
鍼灸が薬を用いない治療であることや、体に作用する不思議さに興味を持ち、鍼灸師を目指すように。 - かいと
鍼灸学科2年生
興味がある分野は中医学・東洋医学。
鍼灸師を目指した理由は鍼灸は学ぶに連れて西洋医学的・東洋医学的2つの面からアプローチできる鍼灸の魅力に引き込まれたから。
好きなことはテニス、音楽を聴くこと。
【ご自愛WEEK】自然に治るし、「葛根湯」飲んでおけば…とはいえ知っておきたい”かぜ”ご自愛
 まりな
まりな今回はテーマであるいわゆる”かぜ”について、東洋医学で学ぶ内容を細かく説明してくれているので、授業の復習にもなりました!
 おかし
おかし東洋医学でも”かぜ”についてやったけど覚えることが多かった気がしたな~
 まりな
まりなかぜ(表証)といえば、“悪寒・発熱・頭痛・項強・脈浮”!!と呪文のように覚えていました!
 おかし
おかしとにかく単語でまずは覚えていくタイプだね!
 まりな
まりなそうですね。
でも、記事ではこれらの症状が出るまでの流れが説明されており、なるほどなぁと思いました。何より、手書きのイラストがわかりやすいだけではなく、かわいいので毎回癒されています(笑)
 おかし
おかしたしかに、イラストがあるとわかりやすいよね!
 まりな
まりな私自身、衛気の作用などは授業の内容として覚えているのですが、実際の臨床の場となると、じゃあ何故、衛気が不足してるんだろう?という原因を特定することが苦手です…。
 おかし
おかしうんうん
 まりな
まりなですが、記事での“普段は衛気が外邪から体を守ってくれているが、その衛気が不足したら営血が衛気となり、さらにその大元の気血を生み出しているのは脾である。”ということを理解していれば、患者さんの症状の原因を繋げていくことができそうです。
 おかし
おかし衛気についてかなり分かりやすく書いてあるんだな…
 まりな
まりなまた、汗の状態でアプローチの仕方が変わるというのが興味深かったです。
汗をかいていれば、お風呂で汗をかくことはさけて漢方薬は桂枝湯を。
汗をかいていなければ、お風呂で汗をかいても良く漢方薬は麻黄湯を。
 おかし
おかしなるほど!かぜの時にお風呂入るか迷うけどかなり参考になりそうだ!さらにオススメの漢方まで記事にあるのか!
 まりな
まりな家族や友人にもこの記事のような東洋医学的な説明や、体調に合った漢方薬をアドバイスできると、中医学が難しいものではなく身近なものになるだろうなと思いました。
「わかっちゃいるけど、やめられない。」に向き合う。明日からできる行動変容アプローチ
 おかし
おかし行動変えるのって中々、難しいよね~
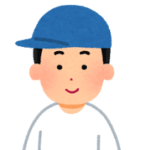 かいと
かいと行動変容アプローチとして“相互性”が大事。
この言葉を見た時に、共感する部分がありました。
 おかし
おかし相互性か…。その共感とは?
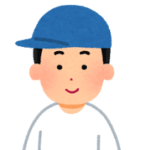 かいと
かいと僕の経験は行動変容とは少し違うと思いますが、高校生の頃、大会前に手首を怪我をして整形外科に行くことがありました。
その際、医師からは2週間ほどは安静にと言われましたが、レギュラーがかかった大事な大会でもあり、「わかってはいるけど、絶対に休めない。」と無理をして練習をしたことがあります。
 おかし
おかしうんうん
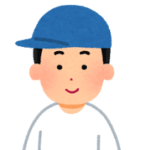 かいと
かいとこの時は、医師側の権力が強い父権主義でしたが、もしお互いに意見が主張できるような“相互性”の関係だったら、結果は変わってきたと思います。
 おかし
おかしお互いが納得できる状態を作れることが望ましいよね。
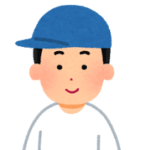 かいと
かいと僕が今まで通院したどの病院でも父権主義の医師はいて、珍しくないんだと思います。だからこそ、相手の「わかっちゃいるけど」の気持ちをしっかりと聴くことが1番大切なんだなと思いました。
 おかし
おかし相手の気持ちを聴くことがうまくできる方法ってあるかなー?
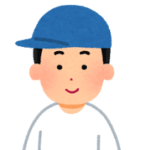 かいと
かいとその為のアプローチとして“LEARNのアプローチ”を行い、相手の心にズバッと響くようなストライクゾーンを見極めることが、患者の行動変容を起こす近道になると思いました。
 おかし
おかし“LEARNのアプローチ”か。はじめて聞いたな!
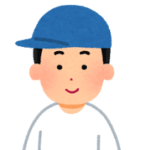 かいと
かいと今回は、“相互性”と“LEARNのアプローチ”この2つが記事の中でも特に、僕がなるほど!と思ったポイントでしたが、この他にも沢山勉強になるポイントがあるので是非読んでもらいたいです!
 おかし
おかし“相互性”と“LEARNのアプローチ”の2つが今回の記事のポイントだね!
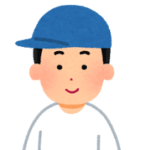 かいと
かいとそうなんです!
今後は、2つのポイントを抑えた上で患者さんや知り合いなど行動変容に困っている人にアプローチしていければいいなと思いました!
 おかし
おかし早く記事を読んで困っている人にアプローチができるようになろう!
麻痺はこうやって評価しよう ~片麻痺に対するフィジカルアセスメント~
 おかし
おかし麻痺の評価!って知っているけどちゃんとできているかわからないな…
 まりな
まりな今回、てっちゃんが示すこの記事での目標は…『明日、片麻痺の患者さんを担当した時に麻痺の運動障害のレベルを正確に把握できるようになること』みたいです!このようにゴールを決めてもらうことで、学ぶことが明確になりますね!
 おかし
おかしということは、記事をみると麻痺の運動障害のレベルを正確に把握できるようになるのかな!?
 まりな
まりな記事では、片麻痺を評価する3つの目的がポイントをしっかりおさえているので要チェックだなと思いました。
 おかし
おかし3つのポイントとは?
 まりな
まりな1.ADLのできる/できないを明確にする
2.機能障害の程度と残存機能を把握する
3.今後起こり得る二次的障害と機能回復を予測するです!
 おかし
おかしなるほど!この3つのことか!
 まりな
まりなまた、読んでいてハッとしたのは、 “あくまで最終的に考えるべきは【日常生活動作(ADL)】がどう変化するか”というところです。 自分だったら、「◯度まで上がるようになりましたね!この調子で頑張りましょう!」 などを言って終わってしまいそうです…。
 おかし
おかしうんうん
 まりな
まりなでも、さらに可動域が広がったことによる日常生活での変化や現在困っていることまで聞きだせるようになるといいですよね!片麻痺の症状は、患者さんが長い期間付き合っていかないといけないものです。
 おかし
おかし動かせる範囲だけよりも日常生活での変化の方が患者さんもわかりやすいよね!
 まりな
まりなそうなんです!日常生活へのちょっとした変化を共有することが患者さんのモチベーションを上げたり、次の目標を決めるためにも大事だなと思いました。
 おかし
おかしそうだね!
 まりな
まりなさらに、連合反応と共同運動の違いも自分の中で曖昧だったので、記事で確認できて良かったです。これによってブルンストロームステージの段階が変わるので、しっかり理解しておく必要があるのを感じました。
 おかし
おかしブルンストロームステージにも書いてあったけど、記事には違いまで書いてあるのか!
 まりな
まりな実習でも片麻痺の患者さんの話を聞いたことがあります。患者さんは分離運動がまだ難しく、「動かしたい方向にどうやって動かせば良いのかわからない」と話していました。
 おかし
おかしうんうん
 まりな
まりな実際の患者さんの様子を思い浮かべながら今回の記事を読むことで、片麻痺の患者さんへのフィジカルアセスメントが理解しやすかったです。
 おかし
おかし今回の記事は何回も読んで勉強することができそうだ!
すぐに読まなくては…
HAMTに興味をもったら
高齢化社会が進む今、訪問鍼灸領域はますます需要が伸びていくことが想定される。
鍼灸師として幅広いフィールドで活躍するためにも、今のうちに知識と視点が広がるこれまでの100記事を超える在宅鍼灸に関する記事がで読み放題の『HAMT〜在宅鍼灸師のためのライブラリ〜』に登録してみてはいかがだろうか。

| お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 白石哲也 | @physio_tetsuya |

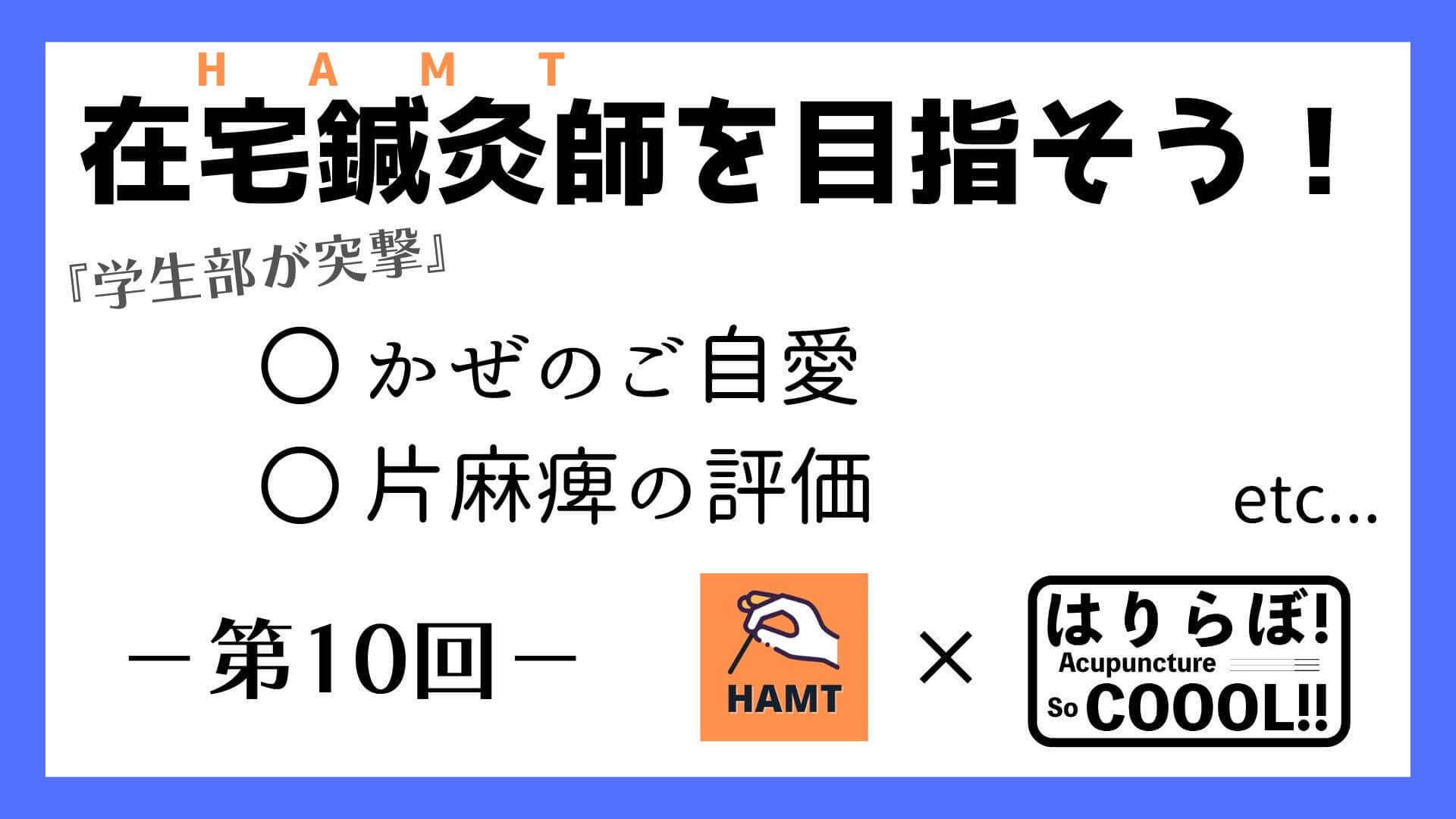


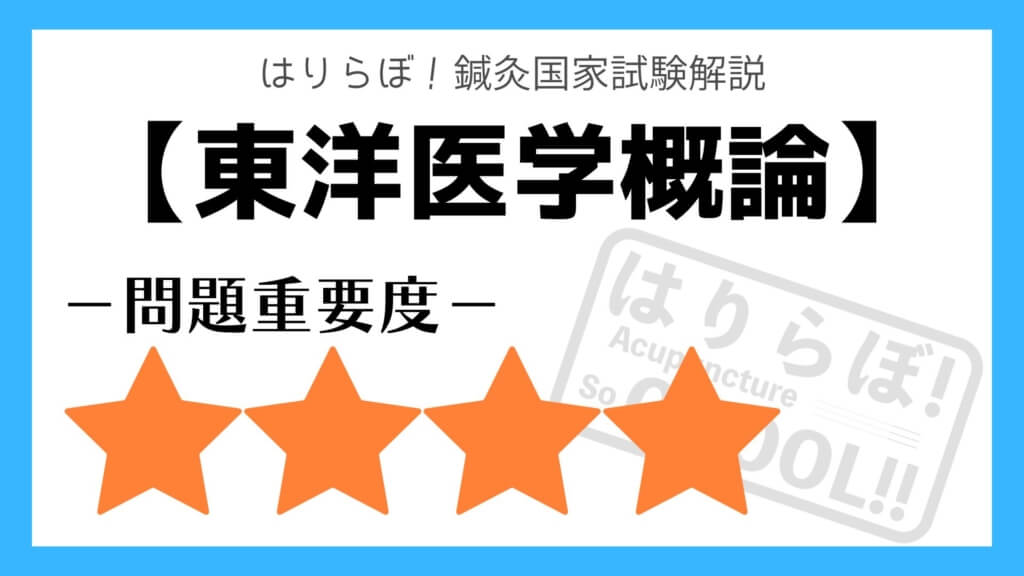
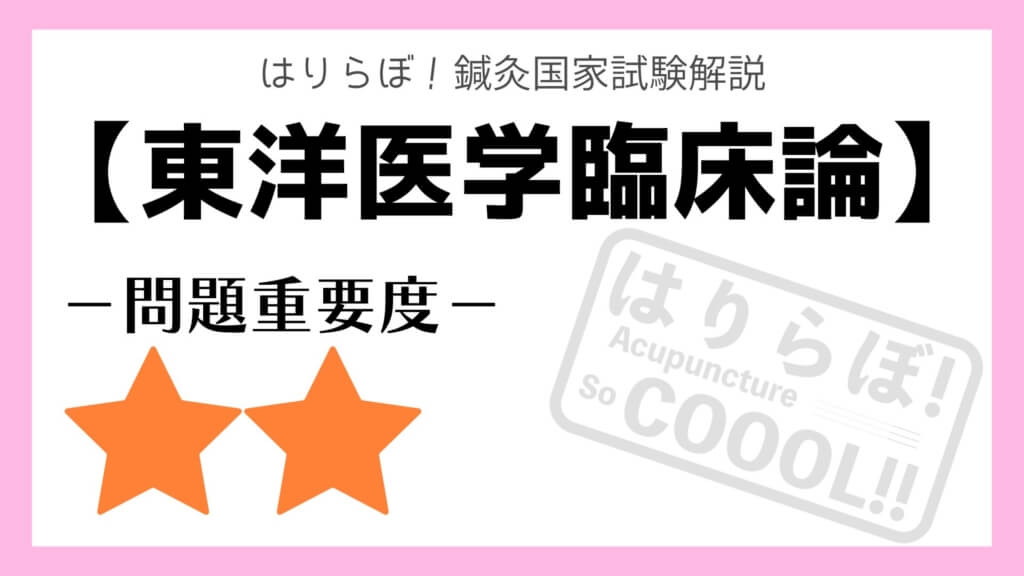
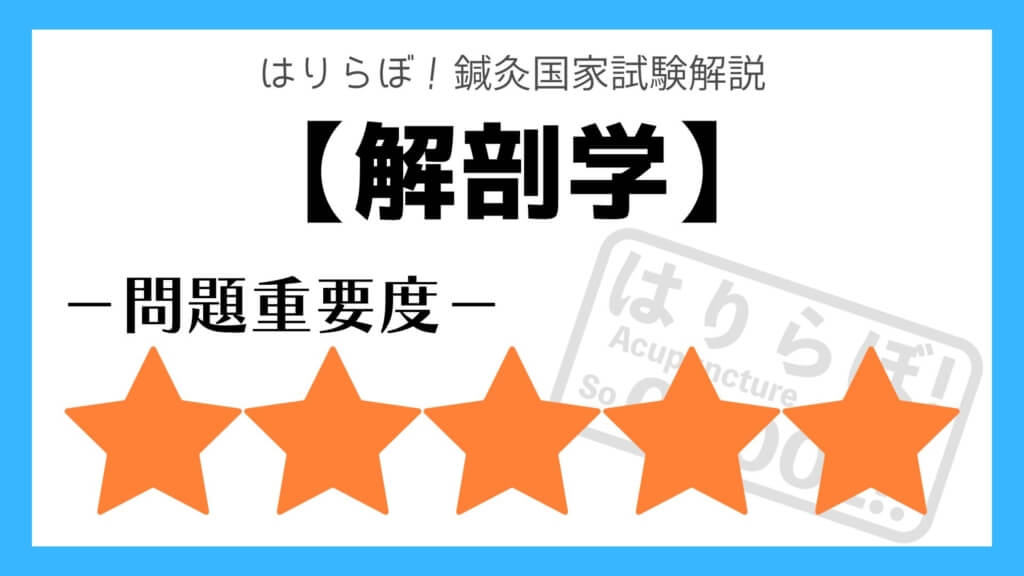
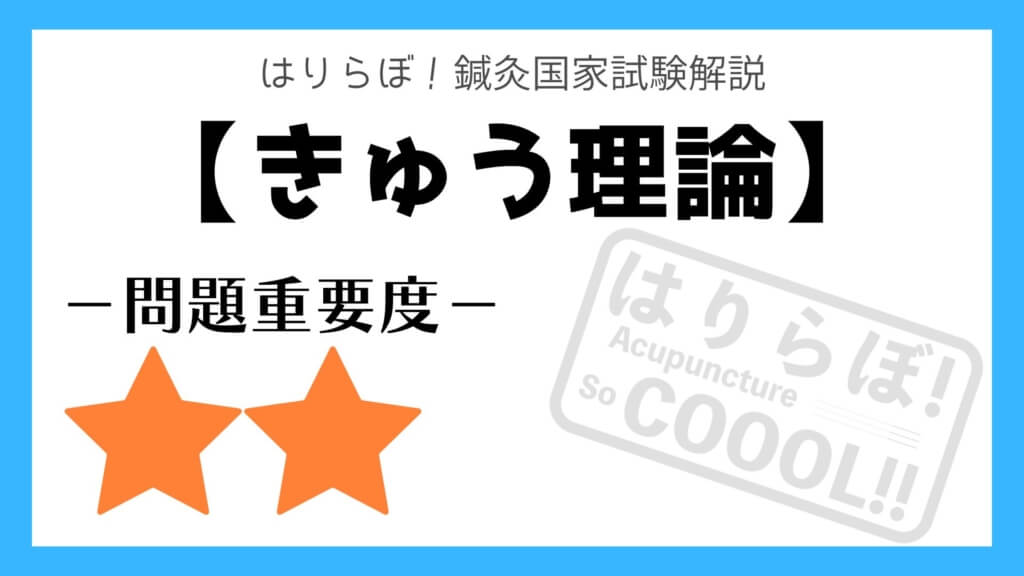
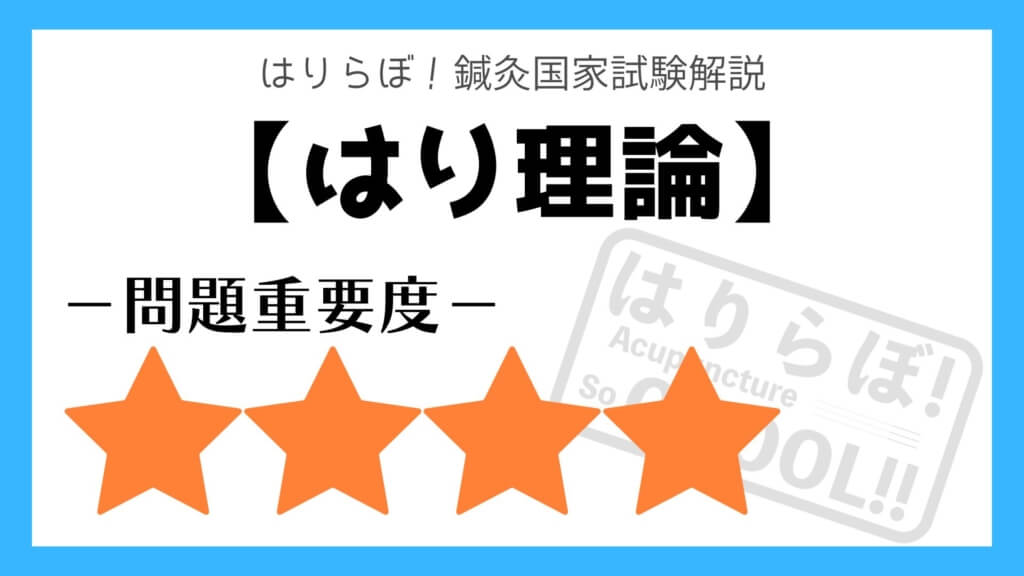
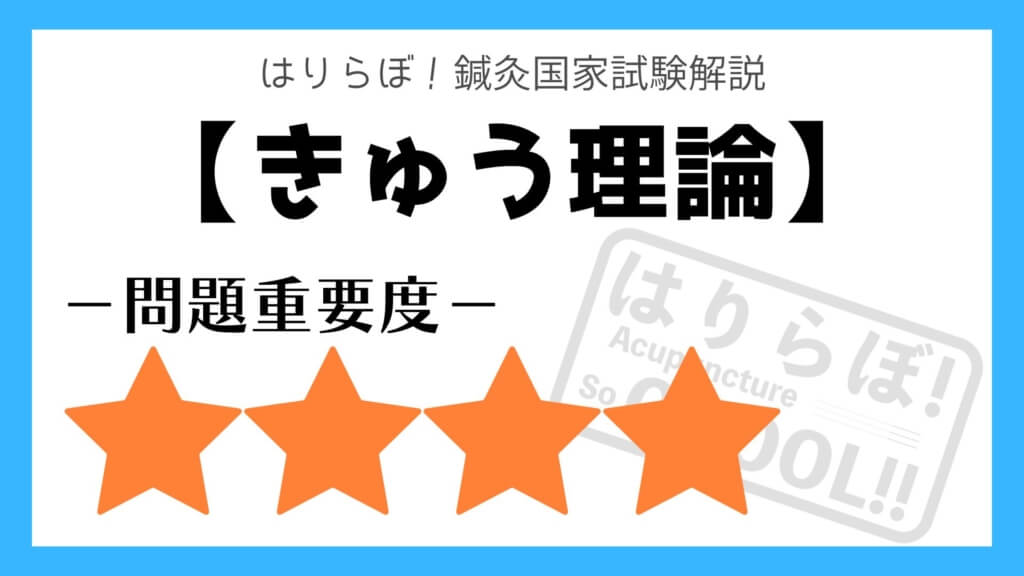
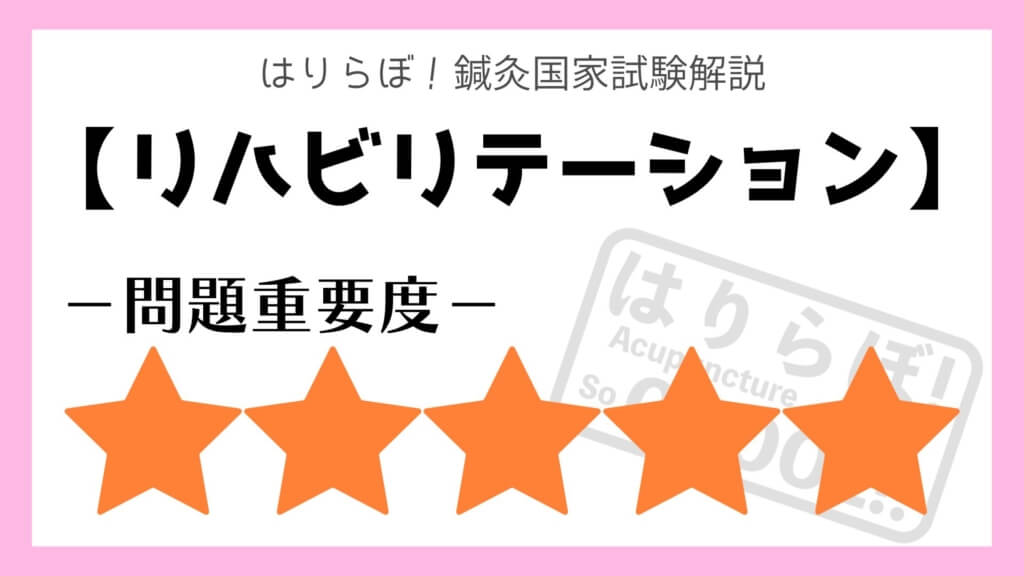
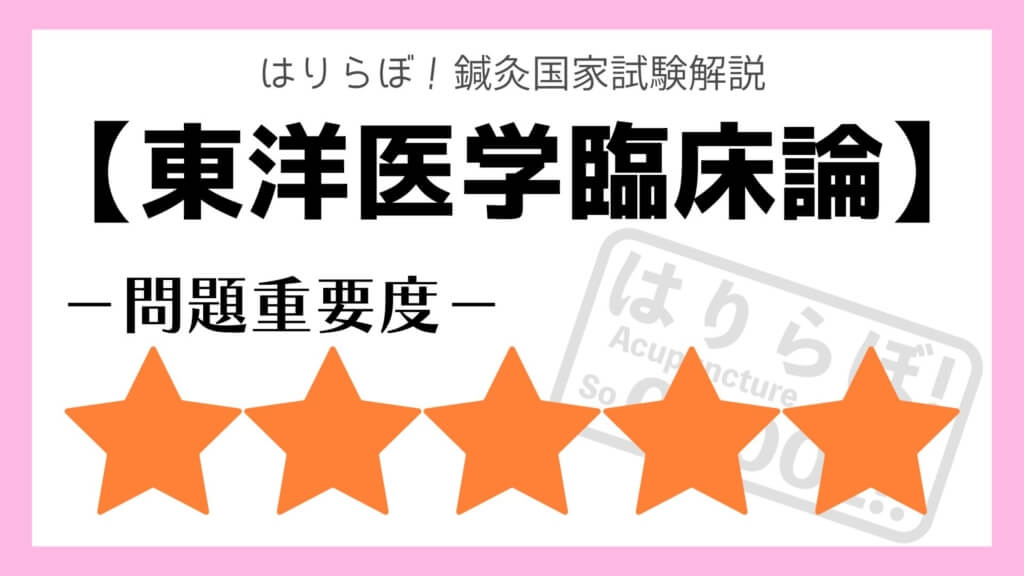

コメント